鍼道五経会の足立です。
前回は「脈診の基準は50拍?」と題して、脈を五十至まで診ることの重要性とその意味について書いてみました。その意味とは「臓気を診る」ことでしたね。(詳しくはコチラ)
しかし、せっかくなので寄り道して経脈の流れと時間の切り口から五十至(もしくはそれに近い基準)について今回は考察を試してみようと思います。
50から連想するのは一日の周回数
50といえば、思い出すのは“1日で気が人体をめぐる回数”です。
※他にも五十は大衍の数としても知られていますがここでは割愛。
人の気は24時間で人体を50周するのです。この辺りの説明は『霊枢』五十営第十五や難経一難に詳しいですね。
日の行(めぐ)り二十八宿、漏水はみな盡(尽)き、脈終わるなり。
所謂、交通とは一数に並び行くなり。
故に五十營備わり得て、天地の壽を盡(尽)くすなり。
『霊枢』(日本内経医学会さん発行)から引用させていただきました。
漏水の下ること百刻、榮衛が陽を行くこと二十五度、陰を行くことまた二十五度で一周となる也。
故に五十度で復(ま)た手の太陰において会する。
寸口は五藏六府の終始する所。故に法、寸口を取るなり。
『難経集註』(日本内経医学会さん発行)から引用させていただきました。
体を気が一周するってどういうこと?
一日で五十周ということは一周はどれくらいか?…というと『霊枢』五十営には書かれています。
気が行くこと中において交わり通り、身において一周する。
水が下ること二刻、日行くこと二十五分。
一日(24時間)=100刻なので、二刻とは24時間の1/50。つまり28.8分で気は人体を一周することになります。このことは以前にもブログで書きましたね。
詳しくはコチラ「経脈を流れる気の速さと呼吸」をどうぞ。
五十至にどのような意味がある?
「脈は五十至は診ないとダメ!」と、そこまで言われるのなら、見せてもらいましょう。五十至の世界とやらを。
ということで計算の基準は『霊枢』五十営のこの記述です。
気行くこと三寸、呼吸定息で気行くこと六寸。」
この記述から考ると、脈の五十至では呼吸は12.5回となります。(一呼一吸で脈四動するという設定)
呼吸十二息半、脈行くこと七尺五寸…なんかピンとこない数字ですね。
ではキリよく二倍にしてみましょう!といっても、息数二十五、脈行十五尺…。
(下表を参照のこと)
| 呼吸 | 脈数 | 脈行 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1周 | 270息 | 1080至 | 1620寸 (16丈2尺) | 2刻(28.8分) |
| 1息 | 4至 | 6寸 | ||
| 10息 | 40至 | 60寸 (6尺) | ||
| 12.5息 | 50至 | 75寸 (7尺5寸) | ||
| 25息 | 100至 | 150寸 (15尺) | ||
| 27息 | 108至 | 162寸 (1丈6尺2寸) | (2.88分) | |
| 50周 | 13500息 | 54000至 | 81000寸 (810丈) | 100刻(1日) |
他にも40至で六尺、50至で七尺五寸、100至で十五尺と、脈診に使えそうな脈数(至)で脈行脈度を出したところ、どれもピンとくる数字ではないですね。
とはいえ、上表の設定は平脈を四至としていますので、次表では基準を五至としてみるとします。
上記では「一呼脉再動、一吸脉再動」の言葉から、単純に再動(二至)+再動(二至)として、呼吸定息、脈四動(四至)としていました。
しかし『素問』平人気象論では、呼吸と呼吸の間(前後の)閏(うるう)を入れて平脈=五至としています。
そして、そもそも脈診の基準は五十動(五十至)です。
| 周回 | 息数 | 脈数 | 脈行 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1周 | 270息 | 1350至 | 1620寸 (16丈2寸) | 2刻(28.8分) |
| 1息 | 5至 | 6寸 | ||
| 10息 | 50至 (五十至) | 60寸 (6尺) | ||
| 12.5息 | 62.5至 | 75寸 (7尺5寸) | ||
| 25息 | 125至 | 150寸 (15尺) | ||
| 27息 | 135至 | 162寸 (1丈6尺2寸) | (2.88分) | |
| 13500息 | 67500至 | 81000寸 (810丈) | 100刻 (1日) |
なぜこんな計算をしているか?
人体を流れる経脈(※)の長さは一周で十六丈二尺とされています。
(※霊枢・難経では左右の十二経すなわち二十四脈に加え、陰蹻脈陽蹻脈、督脈任脈の脈の長さとしている。)
『傷寒論』序文にいう「脈は五十まで診るべき」という基準の根拠を、臓気の絶(霊枢根結や難経十一難脈)とは違う切り口からも、五十動(五十至)の意味を見つけられれば…と思い「呼吸」、「脈行脈度(長さ)」「時間」などと比較してみましたが、どうも納得いく数字はみつかりませんね。
氣行が体を一周するとき(脈度16丈2尺)の脈数は1350至です。この数は一日の呼吸数のちょうど1/10です。
「脈は五十動まで診るべき」はもしかすると、この息数と脈数と脈度(氣行)の関係≪氣行一周・脈度16丈2尺・脈数1350至≫の関係を基にした診法である…かも、と推察することもできそうです。
意味深な数字を考える
では平脈四至と仮定した数字は全く無駄な計算だったのか?とすると、それも寂しいものがあります。こじ付けですが、色々あれこれ考えてみましょう。
脈数(脈至)と脈度の関連性には、意味深な数字が関与しています。
それは…27と108です。
27息のとき脈は108至。
(この時の脈行(脈度)は1丈6尺2寸。人体を一周する距離の1/10)
108といえば煩悩の数ですが、煩悩の数というのもなかなか意味深い数字です。
そして27という数字。これは二十七宿とも関係するか!?と言いたいところですが、月宿には二十七宿と二十八宿の両論あり、インドでは二十七宿、中国では二十八宿が採用されています。
ですので『霊枢』五十営では次のように記されています。
(『霊枢』五十営)
この記述は、天の運行と人の身は相応しているという天人合一説のひとつでもあります。
しかし、27は『霊枢』五十営篇では不採用でしたが、『霊枢』九鍼十二原では二十七気という形で採用されています。
(『霊枢』九鍼十二原)
このように、二十七気は全身を上下めぐる存在として、二十八脈と類似の概念といえます。
とまあ、27という数字は約していくと「3×3×3」のように最小単位は“3”となるわけですが、
27の倍数をピックアップしていくと…
27×3=81…陽の極数である9の二乗数。
81は素問、霊枢、難経にも採用されているおなじみの数。
27×4=108…前述の通り“煩悩”の数。煩悩の数の根拠にも諸説あり。
27×6=162…二十八脈の総数が162尺。
27×10=270…気が人体を一周するときの呼吸数
27×20=540…気が人体を二周するときの呼吸数
27×500=13500…一日における人の呼吸数
27×2000=54000…一日における人の脈数
27×3000=81000…一日における脈行が81000寸すなわち810丈
一日の呼吸・脈行・脈数はそれぞれ13500息、810丈、54000至とありますが、お互いに無関係な数字羅列ではないことが分かり、そこに何らかの思想が見えてきそうです。
例えば、一日の脈行脈度は810丈。
9×9の81の10倍数ですが、9は陽の極数であり、その数字を掛け合わせた数字の10倍ですから、何か意図があるかもしれません。
「如環無端(環の端の無きが如く)」のように絶え間なく循環する流れを意味付ける意図もあったかもしれません。
以上のように、数字に込められた思想や意図、想いなどが垣間見られる“人体にまつわる数字 -中国医学編- ”でした。
元々、中国医学は仏教医学、仏教思想の影響を受けている点からも、二十八、二十七の存在感は大きいと想像します。しかしまだまだ勉強する必要があると思います。またご縁のある専門分野の方に教えを請い、考えていきたいと思います。
と、今回はスッキリしない幕切れでしたが、個人的にはいろいろ考えていて他にも気づいたこともあり、なかなか楽しめたので、ここにも紹介しました。気づきに関してはまた勉強会等で紹介しますね。
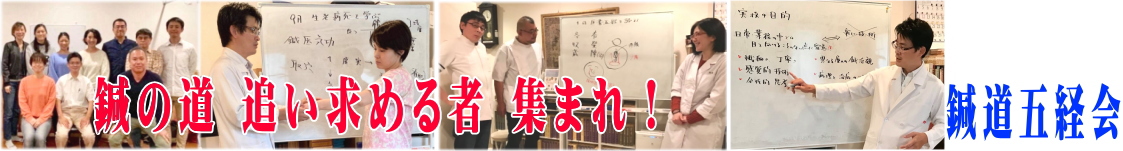

























 TOP
TOP