意外と鍼灸師は脈度を気にしない…
奇経を学ぶシリーズがスタートした。
『十四経発揮和語鈔』の奇経編のアップが終わり、『奇経八脈攷』に移るところだが、
思うところがあり、一旦『難経』に戻ることにする。
まずは『難経』二十三難から、これは『霊枢』脈度篇第十七と同じく、脈の寸法である。
※『難経本義』京都大学付属図書館より引用させていただきました。
※以下に書き下し文、次いで足立のコメントと原文を紹介。
難経二十三難(一部)の書き下し文
手の三陽の脈、手より頭に至る長さ五尺。
五六合せて三丈。手の三陰の脈、手より胸中に至る長さ三尺五寸。
三六して 一丈八尺、五六して 三尺、合せて二丈一尺。
足の三陽の脈、足より頭に至る長さは八尺。六八して 四丈八尺。
足三陰之脈、足より胸に至る、長六尺五寸。六六して 三丈六尺、五六して 三尺、合せて三丈九尺。
人の両足の蹻脈、足より目に至る、長さ七尺五寸。二七して 一丈四尺、二五して 一尺、合せて一丈五尺。
督脈、任脈、各々長さ四尺五寸。二四して 八尺、二五して 一尺、合せて九尺。
凡そ脈の長さ、十六丈二尺。
此れ所謂(いわゆる)十二経脈の長短の数也。
…(後略)
脈の寸法は大切
前回の記事にも書いたが、鍼灸家にとって経脈の寸法を知ることは大事である。
もちろん「寸法を覚えよ」というわけではない。
しかし、経脈は概念的な無形の存在とはいえ、氣血をめぐらすルートである以上、距離が存在するのだ。
故に『霊枢』脉度や『難経』二十三難では、経脈の寸法を手足を起点に「頭」「胸中」「胸」「目」といった地点を目安にして凡その長さを概算として提示している。
『足陽明胃経と足少陽胆経では長さは違いのではないか!?』という意見もあるだろうが、
これはこれで良いと思うのだ。
ではなにが重要なのか?
氣の運行(氣行)には定められた距離(脉度)があり、時間も決まっている。
距離と時間が決まっていれば、速度が求められることは小学校の算数で習ったはずである。
ここから考えると、経脈を流れる氣(営氣)には一定の速度で流行することが分かる。
つまり営気の特徴のひとつとして「時間に基づいた規則性」が挙げられるのだ。
そして、その規則性をもつ営氣が流れるルートとして、督脈・任脈・そして蹻脈(※男女により陰陽が異なる)が選ばれていることにも意味があるのである。
鍼道五経会 足立繁久
二十三難(一部)原文
■原文
二十三難曰、手足三陰三陽脈之度数、可暁以不。
然。手三陽之脈、従手至頭、長五尺。五六合三丈。
手三陰之脈、従手至胸中、長三尺五寸。三六一丈八尺、五六三尺、合二丈一尺。
足三陽之脈、従足至頭、長八尺。六八 四丈八尺。
足三陰之脈、従足至胸、長六尺五寸。六六 三丈六尺、五六 三尺、合三丈九尺。
人両足蹻脈、従足至目、長七尺五寸。二七 一丈四尺、二五 一尺、合一丈五尺。
督脈任脈、各長四尺五寸。二四 八尺、二五 一尺、合九尺。
凡脈長、十六丈二尺。
此所謂十二経脈長短之数也。
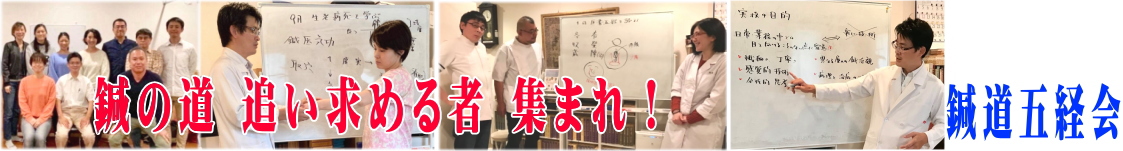

























 TOP
TOP