正経と奇経の違い、なぜ奇経が造られたのか?
【奇経を学ぶシリーズ】の難経編、3回目となる二十七難である。
二十七難では奇経と正経との関係性をはっきりと明示している。
※『難経本義』京都大学付属図書館より引用させていただきました。
※以下に書き下し文、次いで足立のコメントと原文を紹介。
難経二十七難の書き下し文
二十七難に曰く、脈に奇経八脈なる者有り、十二経に於いて拘わらずとは、何の謂いぞ也?
然り。
陽維有り陰維有り、陽蹻有ち陰蹻有り、
衝有り、督有り、任有り、帯の脈有り。
凡そ此れら八脈なる者は、皆 経に拘わらず。
故に曰く、奇経八脈と也。
経に十二有り、絡に十五有り。
凡そ二十七氣は、相い隨いて上下する。
何ぞ獨り経に拘わらざる也?
然り。
聖人、溝渠を圖設し、水道を通利して、以って不然に備う。
天雨降下すれば、溝渠は溢満す。
當に此の時、霶霈妄行すれば、聖人も復び圖ること能わざる也。
此の絡脈満溢すれば、諸経復び拘ること能わざる也。
難経における奇経と正経の関係性
本難は次の二十八難とともに難経の奇経観をよく表わしている。
最後の文「此絡脈満溢、諸経不能復拘也。」は鍼灸師は認識しておくべき経絡観であろう。
経絡はなんとなく鍼して効果がみられる…そんな便利なシステムではないのだ。
治水が大事なのは、国家国土であっても人体であっても同じ。
平時と有事の双方の治め方が必要なのだ。
鍼道五経会 足立繁久
二十七難 原文
■原文
二十七難曰、脈有奇経八脈者、不拘於十二経、何謂也?
然。
有陽維有陰維、有陽蹻有陰蹻、有衝有督有任有帯之脈。
凡此八脈者、皆不拘於経。
故曰、奇経八脈也。
経有十二、絡有十五。凡二十七氣、相隨上下。
何獨不拘於経也?
然。
聖人圖設溝渠、通利水道、以備不然。
天雨降下、溝渠溢満。
當此之時、霶霈妄行、聖人不能復圖也。
此絡脈満溢、諸経不能復拘也。
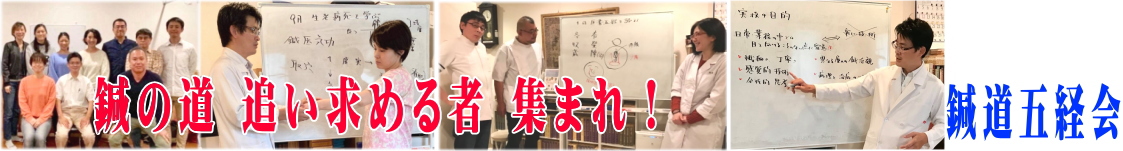

























 TOP
TOP