これまでのあらすじ
前回までは瘟疫の解除後、その回復のために補剤は必要であるが、安易に補気補陽をしてはならない…という内容でした。
補にも陰陽があるわけです。
さて、今回の内容は、下法により陽明腑位から駆邪を行っても、膜原に残存する余邪があるという設定でのお話。膜原という部位の特殊性から、そこに居座る邪の処理がいかにややこしいかが垣間見えてくる内容です。
これまで何度か登場してきた柴胡清燥湯ですが、その処方構成が明らかになります。
(写真・文章ともに四庫醫學叢書『瘟疫論』上海古籍出版社 より引用させていただきました。)
第30章 下後間服緩剤
下後間服緩剤
下後、或いは数下して、膜原に尚餘結(邪)有りて、未だ盡く胃に傳えず、邪熱と衛氣、相い併す。故に熱を頓ろに除くこと能わざれば、當に両日を寛緩にし、餘邪の胃に聚まるを俟ちて、これを再び下すべし。
宜しく柴胡清燥湯の緩剤にて調理すべし。
柴胡清燥湯・・・柴胡、黄芩、陳皮、甘草、花粉(天花粉)、知母
薑棗煎服
また膜原という言葉が登場しました。
下法により陽明腑の邪熱を駆邪したものの、膜原にまだ余邪が残っていて、すべて胃腑(陽明腑)に伝入しきっていなかったという設定です。
その邪氣と衛氣が相搏ではなく、相併との表現には注目すべきでしょう。この表現からも膜原の特殊性が分かります。
膜原とは経胃交関の所(詳しくは第2章【瘟疫初起】)、表裏の間であり、汗下ともに届かない部位であり、衛氣にとっては攻めにくい懐の内側に当るのです。
そのため、直ちに駆邪することができないため、陽明腑に邪が聚まってから再度下法をかけて駆邪するべしとあるのです。
そして陽明腑に邪が聚まるまで、なにもせず手をこまねいているわけにはいきません。放っておくとどのような変証に陥るか分かったものではないからです。
正氣を立て直し、残存する余邪を牽制しつつ、また移動して欲しい病位に誘導しておきたいわけです。
そうすることで戦いを有利に進める…と、このような兵法的な観点は治療家には必要です。
柴胡清燥湯の生薬構成上からみて半表半裏に対し清熱潤燥のフォローを行いつつ、次のステージに病位が移るまで凌ぐような方意だと推察します。
達原飲のように膜原にいる邪を疎利破結するわけでもなく、承気湯のように陽明腑熱を駆逐するわけでもなく、
かといって、養榮湯シリーズのように陰分血分を補充するわけでもない。
このような先を見据えた治療戦略は急性熱病だけでなく、慢性疾患の際にも必要となってくる視点といえるでしょう。
第29章【用参宜忌有前利後害之不同】≪ 第30章【下後間服緩剤】≫ 第31章【下後反痞】
鍼道五経会 足立繁久





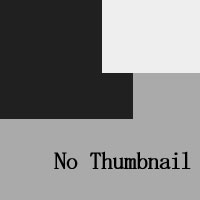




















 TOP
TOP