これまでのあらすじ
前回は「脈証不応」、脈と証(症状)の情報が合わないという非常に臨床的な内容でした。
脈と証が合わない…これは一見したところ、逆証(難治・不治)なのですが、そうではない可治のケースもあります。
そして脈と証の不一致は、瘟疫でなくても意外と普段でも見られることなのです。
さて、今回も同様の内容です。
(写真・文章ともに四庫醫學叢書『瘟疫論』上海古籍出版社 より引用させていただきました。)
體厥
陽證、脉陰、身冷えて、冰の如くなるを體厥と為す。
施幼聲、賣卜(占いを生業)すること頗行、年四旬、禀賦肥甚しなり。
六月に時疫を患い、口燥き、舌乾き、胎刺 鋒の如く、時ならず太息し、咽喉腫痛し、心腹脹満し、これを按して、痛み甚しく、渇して冰水を思い、日晡に益々甚しく、小便赤濇し、涓滴を得るときは則ち痛み甚し。
これ下證、悉く備わる。
但、通身肌表、冰の如し、指甲青黒にして、六脉絲の如く。
これを尋ねるときは則ち有りて、稍按ずれば則ち無し。(※)
醫者、裏證の熱極を究めずして、但、陶氏の全生集の引いて、以て陰證と為す。
但、手足厥逆し、若し冷の肘膝を過ぎれば、便ちこれ陰證なり。
今、已に通身冰冷、これを冷 肘膝を過ぎるに比すれば、更に甚し。
宜なり、それ陰證と為すの一也。且つ陶氏、脉を以て、陰陽の二證を分かつ。全てを有力無力の中に在りて分かつ。
今已に、脉を微にして絶せんと欲す。これを按して無きが如し。
これを無力に比すれば、更に甚し。
宜なり、それ陰證と為すの二也。陰證にして陰脉の至を得る者、何の説有らん。
以て内に諸の陽證 竟に置きて問わず。
遂に附子理中湯を定めるも、未だ服さず。
予を延べて、至る。
脉を以て相い参え、表裏互いに較するに、これ陽證の最たる者にして、下證悉く具わる。
但、下(下法)の晩(おそ)きを嫌うのみ。
蓋し内熱の極みに因りて、氣道壅閉し、乃ち脉微欲絶に至る。これ脉の厥なり。
陽鬱するときは則ち四肢厥逆す。
况や素より、禀肥盛んなるは、尤も壅閉し易し。
今、亢陽已に極まり、以て通身氷冷なるを至す。
これ體厥なり。
六脉無きが如くなる者、羣龍無首の象、證亦危うきなり。
急ぎ大承気湯を投じて、それ嘱して緩緩にこれを下すときは、脉至り厥回し、便ち生を得ん矣。
それ妻は、一は陰證と曰く、一は陽證と曰く、天地懸膈なるを聞きて、疑いて服せず。
更に一醫を請うて、指して言う、陰毒、須らく丹田に灸すべしと。
その兄、三醫を叠延す。
続けて至りて、皆、陰證と言い、妻、乃ち惶惑す。
病者 自ら言う、何ぞ之を神明と卜せざるかと。
遂に卜して、陰に従いて則ち吉、陽に従いて則ち凶とすと得て、更に醫に於いて惑う。
これを陰證と議する者、多く居する、乃ち附子湯を進む。
(附子湯が)咽を下れば火の如く、煩燥頓ろに加わる。
乃ち嘆きて曰く、吾 已りぬ。
薬の誤る所也、言いて未だ已まず。
更に躑躅(毒の意)を加え時を逾(こ)えて乃ち卒す。
嗟乎(ああ)!向きに卜を以って生を謀りて、終に卜を以て死を謀る。人を誤りて還りて自から誤まる。醫巫の鍳と為す。
體厥すなわち体厥をテーマにしつつ、やはり各診法の情報不一致について説かれています。
時疫・瘟疫に罹患して、ことごとく下証(下法を適応とする証、陽明腑実)を備えるのですが、身体の表面や末梢は氷のように冷え込み、脈は糸のように細い…そんな状況です。
※)按・尋とは、脈診の挙・按・尋のことです。
委しく尋ねると脈はかろうじて触知できますが、按じる程度だと脈は触知できなくなる…そんな脈状です。
証は下すべき陽証(厥冷を呈するも)、脈は陰脈…と、これまた脈証不応の状態です。
しかし脈も陰脈にみえて、陽証が極まると現れる脈証だと、呉氏はいいます。
これを陶氏の理論では、脈力の有無のみによって陰証と陽証に分かつのは問題有りだとしています。
その理由は、前章等で詳解している通りです。
そして案の定、前医は陰脈と体厥から、陽気の虚脱であると診断し、附子理中湯を処方します。
しかし、その処方に対して不安を覚えたのでしょうか?
セカンドオピニオンとして呉先生を招聘し、診察を請います。
呉氏の診断は陽証の最たるものであり、下法適応である。
内に陽熱気が鬱しているため、四肢末梢に陽気が回らずに厥冷が起こっているのだと判断します。
ましてや、この人は平素より肥えていて気勢も盛んんなタイプ。
普通の人よりも内なる陽勢が強いのです。当然、内に陽気が結集、壅閉して厥冷が起こりやすくなるのは当然です。
ですから、六脈(左右の寸関尺、もしくは浮沈の寸関尺)が消え入りそうな陰脈を呈するのは、“群龍無首”の象り、すなわち乾卦の用九の言葉を借りて表わしています。
占卜家である患者さん対して小粋な表現です。
そして処方は大承気湯を提示します。
さて、施氏の妻はセカンドオピニオンを得たものの、かたや附子理中湯、かたや大承気湯と、真逆の診断を突き付けられて困ってしまいます。
困った、施氏一家はさらにサードオピニオンを請います。
もうここまで来たら収拾がつかなくなることは必至ですね。
さらにサードオピニオンは陰毒であるから丹田にお灸をすべしと、1stに近い意見を提示されます。
この診断にさらに施婦人は迷います。そんな妻に対して施氏本人が禁断の言葉を放ちます。
「ここは占いだろう!」と。
普段から占卜を生業とする施氏の面目躍如と言いたいところでしょうが、ここまで来たらもうグダグダ。
「群龍首無」とはまさにこのこと。
その結果・・・本文を読んでの通りです。
扁鵲の六不治(『扁鵲倉公傳』を参照のこと)を体現したようなエピソードですね。
医として、治療に携わった者として、徒労感、空虚感に襲われてしまうような結末です。
そして、我々が戒めるべきは、巫・卜を信じ選択した施氏の判断ではありません。
1stオピニオン、3rdオピニオンが共に誤診であったということ。
つまり医療の水準がガタガタなことが問題なのです。
これが呉氏と同じ診断が1人でも下していたら…施婦人の迷走も防げたかもしれません。
そして、水準の不安定さは鍼灸師も自身の問題として自らを省みるべきでしょう。
第48章【脉證不應】≪ 第49章【體厥】≫ 第50章【乗除】
鍼道五経会 足立繁久






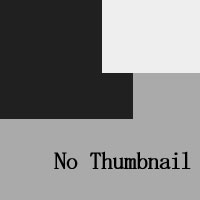



















 TOP
TOP