鍼道五経会の足立です。
診察ってナニ?診断ってナニ?
当会で行っている鍼灸は、診察と診断を重視しています。
鍼灸師には診断権がないと言われてるためなのでしょうか「診断」という言葉に馴染みが薄い印象を受けます。
「診察と診断の違いを説明してみて」というと、困ってしまう初級者が多いですね。
診察と診断にはそれぞれどのような意味があるのでしょうか?
まず東洋医学における診察とは、望聞問切の四診のこと。この四診により多角的に情報を集めます。
何のために情報を集めるのでしょう?
もちろん診断をするためです。診断とは治療方針を決定する行為です。
治療方針があやふやだと、治療そのものにブレが生じます。
学正さんの実技をみていると良くみられる現象に次のようなものがあります。
脈を診て、一通り診察を終え「この人は肝鬱気滞が強いようです。」という学生さん。
さあ治療開始というときに「とりあえず補腎の治療をします」という結論。
このような診察→診断→治療の流れにブレが生じるとこれは治療とは呼べません。
そのような混乱を避けるために当会では、診察技術の向上と診察で得た情報を分析する能力を磨くことに力を入れています。
写真:脈診セミナーで指導する筆者
診察技術の向上とは!?
当会が指導する診察法の中でも特に脈診に力を入れています。
写真:鍼道五経会の脈診
私自身が師から学んだ脈診法は細かく数えて20数種類あります。加えて私が考案した独自の脈診法は5種。
この中から、私自身が臨床で主に使う脈法を勉強会で紹介しています。
もちろん脈診の他にも腹診・背候診、経穴の虚実から得た情報を合参して“診断”を行います。
病理を基に情報を収集する問診も重要な情報源ですね。
これらの情報の性質を考慮しながら診察を行い、スムーズに診断に結びつけるのです。
よく鍼灸師は「治療の経験が大事だ」と言いますが、そんなことはありません。
理に基づいた経験をいくら重ねても、身に着くものといえば「迷い」や「不安」といったものでしょう。
治療において重要なのは【診断】です。(気持ちとか真心とか共感とは置いておきますよ)
では診断することで何を診ているのでしょう?
診断とは病位・病勢・病質を知ること
診断で重要な要素を挙げておきます。
【病位】【虚実(病勢)】【病邪の性質(病邪・病質)】にまとめることができます。
どこに病がいるのか?
例えば重篤な虚証だったとしましょう。
「脾胃が虚しているのか?」「腎が虚しているのか?」「肝陰肝血が虚しているのか?」…これが分からなければ、どんなに優れた補法を行っても無意味です。むしろ間違った場所に補を行うと悪化させます。
119コールを受けたとして“向かうべき現場”が分かってないと、助けようがないのと同じです。
瀉法もまた然りです。
病の本体はどこにいるのかを明確にできると、病邪の処方方法が明確になります。
「邪をどのように動かせば体外に排除できるのか?」ということです。
そのため、より具体的な“病位”そして“体を動かす方向性”のイメージを構築することが必要となります。
実証(虚実判定)だと診断したなら、実の本体はどこに居るのか?(病位)
その実邪の性質は何であるのか?(病邪・病質)
実の勢い、その方向はどこに向かっているのか?(病勢・方向性)
さらにその実はどこからどのような形で追い出したら良いのか?(治法)
と、以上のような治療戦略を決定することが診断において重要なのです。
言い換えると治療ストーリーを明確に構築するということです。
蛇足ながら、補も同じです。
「虚を補うだけで治るのか?」「補した後にどのような治法を必要とするのか?」
といった治療プラン・治療ストーリーですね。
単に「補 瀉を決定するだけ」では不十分であり
病位の対象を「臓・腑・経絡と明確に治療対象を絞ること」が診断であると言えます。
このような鍼灸治療を行うために、当会では脈診や腹診を四診技術を研鑽しています。
第2回「経か?腑か?臓か?を明確に…」に続きます。
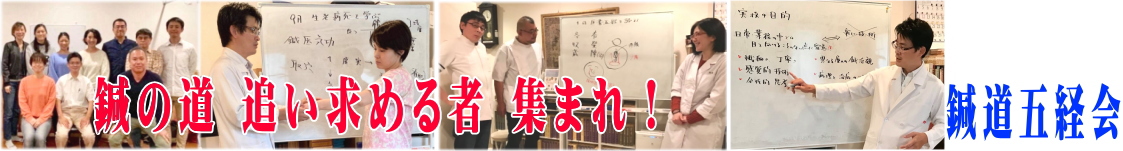

























 TOP
TOP