鍼道五経会の足立です。
前回の【当会で実践する鍼灸その1】をまとめると、以下の2点になります。
・治療において「診断」が要となる
・診断でみるべきは「病位」「病邪・病質」「虚実」を明確にすることである
他にも当会では脈診に力を入れていますが、その点については追々記事にて紹介しましょう。
診断無くして治療無し
鍼灸とはいえ「治療」という以上は「診断」という要素は欠けてはならないのです。
私見ではありますが、鍼灸の弱点はここにあると思います。
病位(病所)の確定が不明瞭なのです。
「病位(病所)は経脈なのか?腑なのか?臓なのか?」
この病位の差により治療内容は全く異なります。
経が病位ならば、経脈の通行を良くします。(経脈への補瀉)
腑が病位ならば、腑を通じさせる。
臓が病んでいるのであれば、臓をたすける。
と、このように鍼法・補瀉を論ずる以前に治療の方向性が大きく異なります。
この病位における“経腑臓の違い”を明瞭しないまま、治療を始めようとする鍼灸学生さん・初学者の方が多いように見受けられます。
この理由を私なりに考えたのですが、これは臓腑経絡システムに起因するのではないかと思うのです。
写真:手太陰肺経の図『十四経発揮和語鈔』より
鍼灸治療は肺経に鍼治や灸治をすることで、太陰肺経を調え、肺藏を調える。さらには表裏関係にある陽明大腸経や母子関係にある腎膀胱に影響を及ぼすことも可能だ。しかし、ここに診断を不明瞭にしてしまう危険性を孕んでいる。
鍼灸治療の弱点とは?
これは鍼灸の長所でもあり、短所でもあります。
病位を「経か?」「腑か?」「臓か?」を明確にしなくても“そこそこ効果が出てしまう”からです。
経絡を調えると、臓腑も調ってしまう。
臓腑を調えると、経絡も調ってしまうからです。
この経絡と臓腑の双方向性の関係は、鍼灸医学の専門領域であり、鍼灸治療の不明瞭さの要因ではないか?と考えています。
この鍼灸治療の不明瞭さを改善する方法が、診断を明確にするという行為なのです。す。
鍼道五経会の追究・実践する鍼灸 その3に続きます。
後日附記
写真:第45回日本伝統鍼灸学会学術大会の実技セッションにて
日本伝統鍼灸学会 金沢大会の本実技セッションでは、経・腑・臓に対する治法の違いについても言及させていただきました。
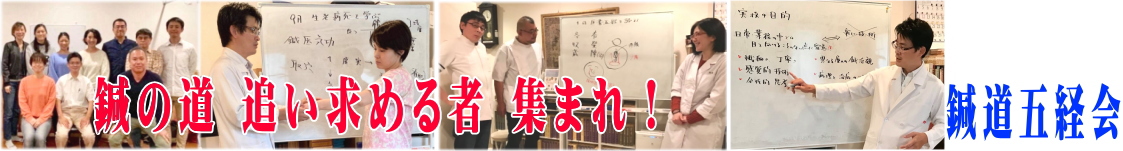

























 TOP
TOP