脈五十至から27と108を考える

伝統医学の一貫性と多様性を学ぶことで道理に至る
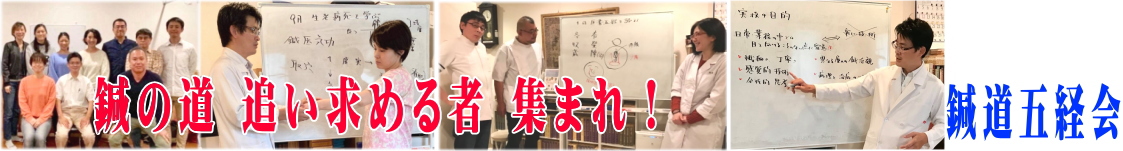

2018/05/23 | category:小児科・小児はり, 講座・生老病死を学ぶ
鍼道五経会の足立です。 先日の日曜日は講座「生老病死を学ぶ」でした。普段は第4日曜日開催なのですが、今月は諸事情で変更し、第3日曜日の開催となりました。 去年の6月からスタートしたこの講座。まだまだ小児科は続きそうです。 ということで、今回の...
読む

2018/05/12 | category:講座・医書五経を学ぶ
5月の第2日曜日定例講座「医書五経を読む」の日。 今回のテーマは脈診3種 午前の治療実技と症例検討の後、脈診を主に学習しました。 今回のテキストは傷寒論の注釈書『医経解惑論』の脈法論です。この『医経解惑論』は私が東洋医学に自信が持てなかった頃、ひたす...
読む