目次
気は感じるもの、考えるモノではない?
職業柄、「気」についていろいろと考察しています。
「気は考えるものではない!感じるものだ!」とお叱りを受けるかもしれませんね、表現を変えましょう。
気を観察しています。
写真:滋賀県の多賀大社 2016年5月撮影
我々は鍼灸学では衛気・営気・宗気と、気を三つに分類していますが、実際はどうなのだろう?
鍼で操作しているのは衛気なのか?営気なのか?
それとも気とは違う別の何かを意識しているのか?
『意外と気について考えることなく鍼しているな…』
『鍼灸師と名乗っているくせに…』などなど、反省するようになりました。
そこから気について観察と考察を続けました。
例えば…
「治療中の自分の気と患者さんの気」
「日常の家族の気、家族に対する自分の気」
「屋外と屋内で自分の取り巻く気の違い」
「アルコール摂取時と非摂取時の気の感じ方の違い」
…などなど、視点をいろいろと変えて気について見直しつつ実験してみたのです。
また、これまでの経験を踏まえ、指導した鍼灸師(鍼灸学生も含む)、出会った治療家(鍼灸師、医師や薬剤師さん等)の行動や振る舞い、人との接し方、その考え方…等々、観察したこと・記憶を基に、東洋医学的な観点から「治療家が扱う気」について考察しました。
その結果、鍼灸師にもいくつかのタイプがあるという結論に至りました。
鍼灸師を4タイプに分ける
衛気を主に操作する衛気タイプの鍼灸師。
営気を主に操作する営気タイプの鍼灸師
湿痰・津液を主ターゲットとする水タイプの鍼灸師
有形の瘀血を主ターゲットとして鍼をうつ鍼灸師
(※厳密にこれら4タイプに分類するわけではなく、各タイプ混合で鍼灸治療を行っているのが実際のところです)
当会立ち上げ当初、こんなことを或る先生と話すと、「ポケモンみたいだね(笑)」と言われたこともあります。
でも その通り! おっしゃる通りでした。
私が個人的に思っていることですので、ポケモンみたいでも、ハンターハンターみたいでもかまいません。
具体的には鍼の使い方や経穴のとらえ方をイメージすると分かりやすいでしょう。
衛気タイプの鍼の使い方
このタイプの先生は、鍼は浅刺を主とします。
むしろ皮膚や肌に接する前から治療が始まります。
速刺速抜の鍼法を使うことが多く、置鍼はあまりしない人が多いです。
動きの早い衛気層に働きかけるので当然ですね。
もちろん、営気層にも鍼しますが主なターゲットが衛気層ということです。
当会にも数名このタイプの先生がいます。
営気タイプの鍼の使い方
このタイプの先生は、浅鍼よりも深い刺鍼を主とします。
営気層を主ターゲットとするので当然です。
経穴も取り方も、虚の強い反応や深い反応を取ります。
深い層に効かせる=遅い動き気を相手にするため置鍼を行っても問題ないでしょう。
多くの鍼灸師は(良くも悪くも)このタイプに属するのではないかと思います。
水タイプの鍼の使い方
気の先にあるものとして「水」や「血」があります。
鍼そのもので水や血を補給したり、排除したりしているわけではありません。
鍼で動くのは気です。
「気を動かした結果、何を動かすのか?」
このように鍼刺の先に何がみえているのか?が重要です。
気を動かした結果、水を動かす。
例えば、汗吐下のように水を動かし、それに伴って気・熱・火をコントロールする。
このような治療イメージは水タイプといえるのではないかと個人的に考えています。
私はこの手の治療を多く使う方です。
血タイプの鍼の使い方
駆瘀血をイメージした鍼を行う先生も多いでしょうが、
東洋医学的な鍼灸でなくても、駆瘀血主体の鍼を使う方もいます。
瘀血は有形(に近い)邪です。
有形の反応といえば硬結があります。
硬結を狙って鍼をする刺法は、東洋医学系の鍼灸師でなくても使う先生は多いでしょう。
無形かつ浅層の衛気とは対極にある存在が有形かつ深層にある瘀血です。
それだけに対瘀血の刺法は太い鍼を用い、深い層にある硬結にしっかりと響かせます。
当会にも数名このタイプの方がいます。
以上、私見ながら気・水・血の視点で分類してみました。
もちろん、この気血水とは違う系統の鍼術分類も可能だと思います。
衛気・営気・血タイプの鍼について、静岡県鍼灸師会中部支部主催にて2021年3月に公開講義を行いました。
その時の受講者の感想がコチラ『いろんな鍼、いろんな鍼灸師の感想』です。参考にしてみてください。
ですが、当会ではこれら4タイプに留まらずもう一つの鍼を模索・追究しています。
さらにもう一つの鍼・治神
衛気・営気・水・血を挙げましたが、その先にあるものとして「神」があります。
言い換えると「神」が衛気・営気・水・血を包括している。
もしくは衛気・営気・水・血に神が宿る…とも表現することも可能です。
「神は細部が宿る」とはミース・ファン・デル・ローエの言葉とされていますが、この言葉にも通ずるようでもあります。
なにより鍼灸師がバイブルと大事にする『素問』『霊枢』には「神」という言葉が頻出します。
「上工は神を守る」 (『霊枢』九鍼十二原)
「神氣の遊行出入する所」(『霊枢』九鍼十二原)
「治神」「凡そ刺の真は、必ず先に神を治むる」(『素問』宝命全形論)
「神を守る」「神を治める」という聞くと、
初心者には『なんだか怪しいゾ…』と思うでしょうし、中級以上ならば『それがどれだけ困難なことか…』と思うでしょう。
しかし、やはりこれまでの鍼灸を含めた治療活動、患者さんを含めた人と人との関わり、赤ちゃん・子どもが成長していく過程…などなどをつぶさに観察することで、『なるほど、内経の云う“神”とはこのような解釈がひとつできるのだな~』と感じ入るようになりました。
これを如何に臨床に応用できるか?は治療家 個々の特性によるでしょう。
「上工は神を守る」という通り、そう簡単なものではありません。ですが、意外と意識せずに偶発的に再現していることもあるかもしれません。だからこそ難しいのですが…。
この「治神」を含めて五経の鍼となります。
ちょっとディープな話になるので、一旦「衛気・営気・水・血の鍼」の話に戻ります。
結局どのタイプがベストなの?
以上、鍼灸を4つのタイプに分類してみましたが、念をおしておく必要があります。
『どれが正しい鍼なのか?』『どのタイプが理想的なのか?』について話しているわけではありません。
それぞれのタイプに優劣をつける必要はないのです。
似たような話題はよく耳にしますよね。
例えば、衛氣タイプの先生は深い鍼や強い刺激を好みません。
「そんな鍼をしたら効かせ過ぎ!患者さんがしんどくなる!」
と否定的な立場にあることが多いです。
同様に瘀血タイプの先生は、浅い鍼を好みません。
「そんな刺激で本当に効くのだろうか?患者さんは満足するの?」
と、これまた懐疑的であります。
重要なのは、どちらの鍼が正しいかではなく、
自分の気質に合った刺法を磨くことです。
そして現場では、患者さんの気質に適した刺法をその場で選択し実践できる能力が必要です。
少し似たような話に「鍼灸師のタイプと好み」があります。
鍼灸治療の手技選択と好みやその人の体質に相関関係があるかも…という記事です。
指導者の視点から
教えを受ける側として心がけるべきは、自分の気質を正しく理解することが大事です。
でも端(はな)からそれが分かれば苦労はしないし、勉強会にも行かないですよね。
となると、指導者の存在が重要となります。
指導する立場としても、何を指導しているのか?
自分の得意技を指導するだけに陥っていないか?
常々自問自答する必要があります。
理想の指導者としては、生徒や弟子の気質・タイプを見抜いて、
それぞれに合った刺法・鍼法を指導・伝授できる指導者であることです。
ということで、私自身も今後さらに日々の精進・切磋琢磨が必要だと感じる次第です。
鍼道五経会 足立繁久
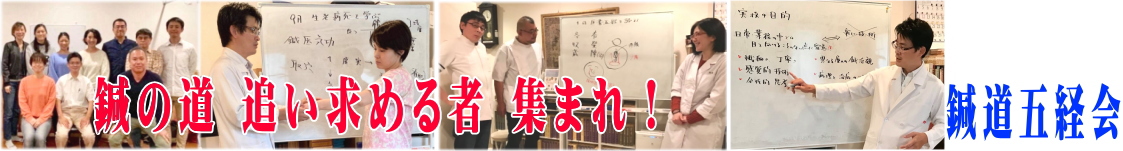

























 TOP
TOP
コメント
[…] このように「敵を知り己をしれば百戦危うからず。」という孫氏の言葉通りですね。 (己を知るとはコチラの記事 → あなたは何タイプの鍼灸師?) […]
by 各診法の違い-脈診と腹診と望診- | 鍼道五経会 2019年2月26日 9:05 PM