目次
中国医学の五大治法 ー方位と治法の意ー
前回の「中国医学 五大治法と六つめの治術・その1」では五大治法として、砭石・湯液・灸焫・微針・導引按蹻を紹介しました。
『素問』異法方宜論第十二では、各治法と各方位が相当しており、各治法にはそれぞれの意が込められていたことを学びました。
第2回では、五大治法に連なるもう一つの治術を紹介します。
もう一つの治術、その名を「祝由(しゅくゆう)」といいます。
もう一つの治術、祝由は移精変氣第十三にある
祝由(しゅくゆう)は異法方宜論第十二の次の移精変氣論第十三にあります。
この2つの連続した論において祝由の存在は大きいと私は思います。
まず移精変氣という言葉そのものが意味深です。
「精を移し氣に変ずる」
中国医学の臓腑観では、精は腎に蔵され、神と対となる存在です。
また道教・内丹では、精氣神を三宝とし、修行段階に「煉精化気」「煉気化神」
すなわち精を煉り氣と化すという段階があります。
内経の移精変氣論では以下のように祝由について解説されています。
〔足立シンプル意訳〕
今より昔は、精を移し氣を変じ、祝由によって病は治っていた。
しかし、今の時代は違う。
憂苦の心は人の情や形体を害し、邪気の侵入を容易くしてしまう。
そのため、軽病であっても重病に発展し、
重病は死に至るというケースもある。
世の人を祝由で病を医することは難しくなっている。
以上、不肖 足立による意訳になります。
以下の黄色枠は移精変氣論の書き下し文です。
※移精変氣論の全文書き下し、及び原文は記事の最後に載せています。
惟だ、それ精を移し氣を変じ、祝由して已(いやす)べし。
今の世の治病、毒薬(湯液)にてその内を治し、鍼石にてその外を治す。
或いは癒え、或いは癒えず。何ぞや。
岐伯対て曰く、往古の人、禽獣の間に居り、動作して以て寒を避け、陰居して以て暑を避ける。
内に眷慕の累無く、外に伸官の形無し。これ恬憺の世、邪は深く入ること能はざる也。
故に毒薬(湯液)はその内を治すること能はず、鍼石はその外を治すること能はざる。故に移精変氣を加え、祝由して已るべし。
当に今の世は然らず。憂患はその内に縁り、形に苦しみその外を傷る。
又、四時の従を失い、寒暑の宜しきを逆らう。賊風は数々至り、虚邪は朝夕にす。
内、五臓骨髄に至り、外、空竅肌膚を傷る。小病、必ず甚しく、大病は必ず死する所以。
故に祝由にて已すこと能はざる也。…(後略)…
…と以上のように、生活環境の変化によって人は体質のみならず人心にも変化が起こります。
その結果、祝由という術の有効性が低下してしまった・・・ということでしょうか。
祝由とはどのような治術なのか?
では祝由とは一体どのような治術なのでしょう?
内科、婦人科、小児科などと同様に祝由科という科が医療の中に存在していた時代もありました。
同じく内経の『霊枢』賊風第五十八にも、祝由に関する一節があります。まずは不肖 足立による意訳から…。
〔足立シンプル意訳〕
黄帝が質問される。祝由によって治癒するケースがあるが、その理由はなぜだろうか?
岐伯先生が答えます。祝由を行う巫医は、百病の法則を知っています。
すでに病の生じる理由、病因と病理とその性質を把握しています。
それ故に病の由を祝して治癒するのです。
以下の黄色枠に『霊枢』賊風篇の一節を書き下し文として載せます。
※『霊枢』賊風第五十八の原文は記事末に載せています。
賊風篇の文では、「百病の勝」「病の従い生まれる所」が祝由の鍵となるようにみえます。
『霊枢』賊風第五十八では、邪氣が人体を傷害する機序を説明しており、病因病理そして診断の要素が感じられます。
同じ祝由をテーマとしていても、移精変氣論とは趣きが異なるように感じるのは私だけでしょうか。
ここで歴代の医家たちがどのように祝由を理解していたかを覗いてみましょう。
歴代の医家たちは祝由をどうみたか?
祝由は謎のベールに包まれているのは今も昔も同じようで、歴代の名医たちも祝由について論を展開しています。
それぞれを調べていくと、インフォームドコンセント派、小病しか治せない派、精神感応派の大きく3つに分類できるかと思います。
以下にそれぞれの代表例を紹介します。
インフォームドコンセント派
インフォームドコンセントというと語弊がありますが…
その主旨は「病の原因を理解し、患者に説明し、治癒と再発防止に役立てる」という極めて理性的で現代医学的な説です。
その代表格と言えるのが呉鞠通。温病学派で知られた先生です。
呉鞠通の著書『醫醫病書』(1833年)十七治内傷須祝由論では次のような言葉があります。
上は足立の意訳、下が原文の抜萃になります。(以下の黄色枠も同様です)
祝とは告げる、由とは出の所以(ゆえん)である。近頃は巫術をもって祝由科とし、十三科の中に列しているが、
『内経』ではそもそも「巫を信じて医を信ぜずを不治」としている。巫を医科の中に列するのはいかがなものか?
私は、凡そ内傷病を治する際には、必ず先に祝由を行う。病の由来を詳しく告げることで、病人にこれ(病因)を知らしめ、敢えて再び犯させないようにする。…」按祝由二字、出自『素問』。祝、告也。由、病之所以出也。近時以巫家為祝由科,並列於十三科之中。
『内経』謂信巫不信醫、不治。巫豈可列之醫科中哉。吾謂凡治內傷者、必先祝由。詳告以病之所由来、使病人知之、而不敢再犯。
又必細體變風變雅、曲察勞人思婦之隱情、婉言以開導之、荘言以振驚之、危言以悚懼之、必使之心悅情服、而後可以奏效如神。
餘一生得力於此不少、有必不可治之病、如單腹脹、木乘土、於血癆、噎食、反胃、癲狂之類、不可枚舉。
葉氏案中謂無情之草木、不能治有情之病、亦此義也。俗語云有四等難治之人、老僧、寡婦、室女、童男是也。有四等難治之病、酒、色、財、氣是也。難治之人、難治之病,須憑三寸不爛之舌以治之。救人之苦心、敢以告来者。
『醫醫病書』十七治内傷須祝由論(呉鞠通 著)より
(手持ちに『醫醫病書』がないため中國哲學書電子化計劃さんの資料を参考にさせていただきました。)
なるほど、さすが呉先生。
たしかに病に対する理解を治療サイドと患者サイドの両方に求めることで質の良い医療を実現することができることでしょう。病の由来を伝える手段として祝由を位置づけている例です。
小病しか治療できない派?
「病は気から」との言葉の通り、感受性が強く、影響されやすい人が罹る病に祝由は効果的である。
つまり軽病(小病)にしか祝由は効かない。
…と、こんな風に祝由をとらえている医家もいます。
こんな風にいわれると内経(移精変氣論)以前の病人は、すべて(いろんな意味で)軽い人たちだったのか?なんてツッコミを入れたくなりますが…。
この「祝由が有効なのは小病くらいじゃないの?」と、どちらかといえば祝由には否定的な意見が多いように感じます。これらの医家たちには虞天民、徐大椿、朱丹渓のような方々がいます。
虞天民はその著書『医学正伝』(1515年)の或問のひとつに祝由について以下のように触れられています。
※画像は『(京板校正大字)医学正伝 8巻』(京都大学附属図書館所蔵)部分より引用させていただきました。
曰く、禁咒科の者は、即ち素問の祝由科なり。龍樹居士に於ける立教を、移精変気の術と為すのみ。
小病、或いは男女神廟に入り驚惑して病を成す、或いは山林溪谷の悪氣に衝斥するを治すべし。
呪(咒)語を借りるを以て、惑を解し神を安んずるを以て已むべし。
今は流れて而して師巫と為り、降童と為り、師婆と為りて、人民を扇ぎたて惑わす、哄嚇取財の術と為るなり。
ああ、邪術はただ邪人がこれを用いる、理を知る者は用いる勿れ也。「或問、古者毉家有禁咒一科、今何不用。
曰、禁咒科者、即素問祝由科也、立教於龍樹居士、為移精變氣之術耳。
可治小病、或男女入神廟驚惑成病、或山林溪谷衝斥悪氣、其証如酔如痴、如為邪鬼所附、一切心神惶惑之証。
可以借呪(咒)語以解惑安神而已。古有龍樹呪法之書行于世、
今流而為師巫、為降童,為師婆、而為扇惑人民、哄嚇取財之術。噫、邪術惟邪人用之、知理者勿用也。」
『医学正伝』巻一 或問 凡五十一條より
虞天民は祝由を龍樹居士(ナーガルージュナ)の教えとし、仏教との関連を示唆しているがどうなのだろう…。
ともあれ「咒語・呪文を使って、惑いを解消し精神を安定させることで癒す。」としており、
今風に言うと、祝詞やお経を唱えつつ、悩みの根源を解くことで、精神を安定させる…ということでしょうか。
平成の人間が祝詞やお経や呪文なんて聞くと、怪しい新興宗教か!?と思われがちですね。
とはいえ、邪術を行うは邪な人、との痛烈な批判もあり、今も昔もこの辺りは変わっていないということでしょうか…。
さて徐大椿の意見は『医学源流論』(1757年)では以下の通り
※画像は『医学源流論』(京都大学附属図書館所蔵)部分より引用させていただきました。
若し果して病機深く重い者には、また效有ること能わざる也。
古の法は今に伝わらず。近くに伝える所は符咒の術。まま小さな効は有るが、病の大なる者には全く功は見られず。
蓋し岐伯の時に已に然れば、况んや後の世をや。存じて論じるべからざる也。」
祝由之法、内経賊風篇岐伯曰、先巫知百病之勝、先知其病所従生者、可祝而已也。又移精變氣論岐伯云、古恬憺之世、邪不能深入、故可移精祝由而已。
今人虚邪賊風、内着五臓骨髓、外傷空竅肌膚、所以小病必甚、大病必死、故祝由不能已也。
由此観之、則祝由之法、亦不過因其病情之所由、而宣意導氣、以釋疑而解惑。此亦必病之軽者、或有感應之理。若果病機深重、亦不能有效也。古法今已不傳、近所傳符咒之術。間有小効、而病之大者全不見功。盖岐伯之時已然、况后世哉。存而不論可也。
『医学源流論』下巻 祝由科論より
「意を宣べて氣を導く」とあり、精神不安を解消することで気の滞りを解き、気を導くと言っています。
この程度で治るということは、よほどの軽症か思い込みの強い人だというスタンスです。
金元四大家のひとり、朱丹渓も『格致余論』(1347年)の虚病痰病有似邪祟論では、移精変氣については小術にすぎないと否定的に意見を残しています。
『外臺秘要』には禁呪の一科があるが、この法は凡庸な医が廃れさせたのだろうか?という問いかけに対し、
朱丹渓は「移精変氣は小術にすぎず、小病を治すのみである。もし内に虚邪があり、外に実邪があれば、治療はまさに正大の法(湯液による治療)を用いるべきである。…(略)」
と問答形式で自身の考えを述べています。
※『外臺秘要』には禁呪科は見られず、『千金翼方』のことを指しているのかもしれません。
彼我の神を相合する派
さて最後に紹介するのが高士宗 先生の説。術者と患者、両者の神をどうこうするという話です。
高士宗は『素問直解』(1695年)において神、精、氣の言葉を用いて、移精変氣および祝由の解説をしています。実に興味深い説ですので、ちょっと多めに以下に抜粋しますね。
惟だ上古の祝由による治病は、能く精を移し氣を変じ、色脈を理して神明を通ず。
我の神を以て、彼の神に合し、両(ふた)つの神が相い合して、精氣が相い通ず。故に祝由にして已むべし。今時の人は能わざる也。
精氣は神を以て主と為す。故に曰く神を得る者は昌、神を失う者は亡すと。
・・・
導引これを移と謂う、振作これを変と謂う。
祝由なる者、その病の由来となる所を祝し、以って神に告げる也。
上古に毒薬は未だ興らず、針石も未だ起きず、惟だその移精変気が、祝由してその病を已むべし。
今世の治病、祝由を憚ること無く、毒藥を用い以ってその内を治し、鍼石で以ってその外を治す、
その病、或いは癒え、或いは癒えず、その故は何ぞや?
・・・
往古の人は禽獸の間に居し、天寒ければ動作するを以て避寒し、天暑ければ則ち陰居するを以って避暑す。…內に眷慕の累は無く…外に伸官之形も無し。…
内外ともに安和すれば、この恬憺の世に外邪は(人体に)深く入ること能わざる也。
内は無病である故に毒薬はその内を治すること能はず。
外が無病である故に鍼石はその外を治すること能わず。
氣機に微しく和せざる故に移精変氣をすべし。由を祝して以て神に告して、病は即ち已える。『素問直解』移精変氣論第十三篇(1695年 高士宗)より
我の神と彼の神を合わせるという表現がなかなか妙であります。
彼我の両神をあわせることで精と氣が相通ずる。それが成されてこその祝由であると言っています。
『霊枢』本神では、両精が相搏つことを神と謂うとありますが、これとはまた異なるプロセスであります。
また「祝由なる者、その病の由来となる所を祝し、以って神に告げる也。」とあり、呉鞠通の「祝とは告げる」と同じようにみえて、告げる対象が違うことにも注目すべきでしょう。
高士宗先生の祝由に対する説は興味深く、まだ掘り下げるべき点もあるでしょうが、一旦ここまでとします。
今回は祝由について『素問』『霊枢』における各説と、後代の医家たちが祝由をどのように解釈したか?について紹介しました。
次回は江戸期の日本の医家たちがどのように祝由を解し、実際に活用したていたか?を紹介します。
『素問』移精変氣論第十三の全文および原文
惟だ、それ精を移し氣を変じ、祝由して已(いやす)べし。
今の世の治病、毒薬(湯液)にてその内を治し、鍼石にてその外を治す。
或いは癒え、或いは癒えず。何ぞや。岐伯対て曰く、往古の人、禽獣の間に居り、動作して以て寒を避け、陰居して以て暑を避ける。
内に眷慕の累無く、外に伸官の形無し。
これ恬憺の世、邪は深く入ること能はざる也。
故に毒薬(湯液)はその内を治すること能はず、鍼石はその外を治すること能はざる。
故に移精変氣を加え、祝由して已るべし。
当に今の世は然らず。
憂患はその内に縁り、形に苦しみその外を傷る。
又、四時の従を失い、寒暑の宜しきを逆らう。
賊風は数々至り、虚邪は朝夕にす。
内、五臓骨髄に至り、外、空竅肌膚を傷る。
小病、必ず甚しく、大病は必ず死する所以。
故に祝由にて已すこと能はざる也。
帝曰く、善し。余、病人に臨みて、死生を観、嫌疑を決せんと欲す。
その要、日月の光の如くなること知らんと欲す。得て聞くこと可けんや。
岐伯曰く、色脈は、上帝の貴ぶ所なり。先師の伝える所なり。
上古、僦貸季をして、色脈を理して神明に通ず。
これを金木水火土、四時八風六合に合し、その常を離れず。
変化すること相い移りて、以ってその妙を観、以ってその要を知る。
その要を知らんと欲すれば、則ち色脈是なり。
色、以て日に応じ、脈、以て月に応ず。
常にその要を求めれば、則ち其の要なり。その色脈の変化、以て四時の脈に応ず。
これ上帝の貴ぶ所にして、以て神明に合する也。
死を遠ざけて生を近くす所以。生道以て長ず。
命じて聖王と曰う。中古の治病、至りて之を治す。
湯液十日、以て八風五痺の病を去る。
十日にして已ざれば、治するに草蘇、草奒の枝を以て、本末の助と為す。
標本已に得て、邪氣すなわち服す。暮世の治病や、則ち然らず。
治、四時に本づかず、日月を知らず、逆従に審せず。
病形已に成りて、すなわり微鍼その外を治し、湯液その内を治せんと欲す。
麤工、兇兇として、以て攻めるべしと為し、
故病未だ已えず、新病復た起こる。
帝曰く、願くば要道を聞かん。
岐伯曰く、治の要極、色脈を失うこと無し。
之を用いるに惑わずは、治の大則。
逆従到り行われ、標本得ざるは、神を亡い国を失う。
故を去り、新に就けば、すなわち眞人を得る。黄帝曰く、余、その要を夫子に聞く。
夫子が言う、色脈を離れず。これ余の知る所なり。
岐伯曰く、之を治すること一に於いて極むる。帝曰く、何を一と謂うか。
岐伯曰く、一なる者は因りて之を得る。帝曰く、奈何なるか。
岐伯曰く、戸を閉じ牖を塞ぎ、これを病者に繋ぎ、数々その情を問い、以てその意に従う。
神を得る者は昌にして、神を失う者は亡ぶ。
帝曰、善し。
『素問』移精変氣論第十三の原文
『素問』移精変氣論第十三
黄帝問曰、余聞古之治病、惟其移精変氣、可祝由而已。
今世治病、毒薬治其内、鍼石治其外、或癒或不癒、何也。
岐伯対曰、往古人居禽獣之間、動作以避寒、陰居以避暑。
内無眷慕之累、外無伸官之形。
此恬憺之世、邪不能深入也。
故毒薬不能治其内、鍼石不能治其外、故加移精変氣祝由而已。
當今之世不然、憂患縁其内、苦形傷其外。
又失四時之従、逆寒暑之宜、賊風数至、虚邪朝夕。
内至五臓骨髄、外傷空竅肌膚、所以小病必甚、大病必死。
故祝由不能已也。
帝曰、善。
余欲臨病人、観死生、決嫌疑、欲知其要如日月光、可得聞乎。
岐伯曰、色脈者、上帝之所貴也。
先師之所傳也。上古使僦貸季、理色脈而通神明、合之金木水火土、四時八風六合不離其常。
変化相移、以観其妙、以知其要。
欲知其要、則色脈是矣。
色以応日、脈以応月。常求其要、則其要也。
其色脈之変化、以応四時之脈、此上帝之所貴、以合於神明也。
所以遠死而近生。生道以長、命曰聖王。
中古之治病、至而治之、湯液十日、以去八風五痺之病。
十日不已、治以草蘇、草奒之枝、本末為助、標本已得、邪氣乃服。
暮世之治病也、則不然。
治不本四時、不知日月、不審逆従、病形已成、乃欲微鍼治其外、湯液治其内。
粗工兇兇、以為可攻、故病未已、新病復起。
帝曰、願聞要道。
岐伯曰、治之要極、無失色脈、用之不惑、治之大則。
逆従到行、標本不得、亡神失國、去故就新、乃得眞人。
黄帝曰、余聞其要於夫子矣。
夫子言不離色脈、此余之所知也。
岐伯曰、治之極於一。
帝曰、何謂一。
岐伯曰、一者因得之。
帝曰く、奈何。
岐伯曰、閉戸塞牖、繋之病者、数問其情。
以従其意、得神者昌、失神者亡。
帝曰、善。
『霊枢』賊風第五十八の原文
岐伯曰、此皆嘗有所傷於湿気、藏於血脈之中、分肉之中、久留而不去。若有所堕墜、悪血在内而不去。卒然喜怒不節、飲食不適、寒温不時、腠理閉而不通、其開而遇風熱、則血気凝結、與故邪相襲、則為寒痹。其有熱則汗出、汗出則受風、雖不遇賊風邪気、必有因加而發焉。
黄帝曰、今夫子之所言者、皆病人之所自知也。其毋所遇邪気、又毋怵惕之所志、卒然而病者、其故何也。唯有因鬼神之事乎。岐伯曰、此亦有故邪、留而未發、因而志有所悪、及有所慕、血気内乱、両氣相搏。其所従来者微、視之不見、聴而不聞、故似鬼神。
黄帝曰、其祝而已者、其故何也。
岐伯曰、先巫者、因知百病之勝、先知其病之所従生者、可
祝而已也。


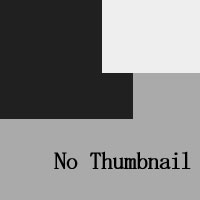



















 TOP
TOP