脈診の三機(脈機)について

伝統医学の一貫性と多様性を学ぶことで道理に至る
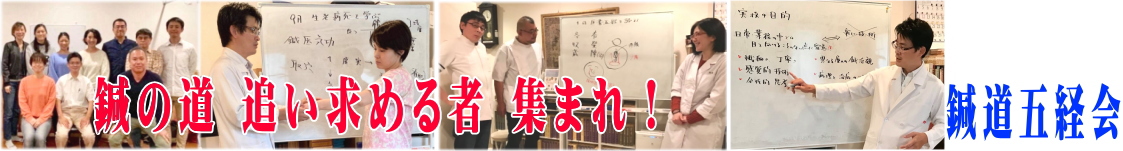

2017/08/30 | category:脈診のはなし, 講座・医書五経を学ぶ
先日は【医書五経を読む】の3回目でした。 第1回は平旦(へいたん)について 第2回は海と精明の府について そして今回(3回)は望診と死脈についてが主なテーマでした。 1回から3回ともに『素問』の脈要精微論を最初から読み進めているのですが、脈要精...
読む

2017/06/12 | category:脈診のはなし, 講座・医書五経を学ぶ
鍼道五経会の足立です。 昨日は講座『医書五経を読もう』の第1回をスタートしました。 “やさしい素問の脈診”をテーマに、脈要精微論第十七から勉強しました。 脈要精微論は「診法は常に平旦をもってす」という内容から始まります。 平旦とは明け方...
読む