目次
金元四大家のひとり、李東垣
中国医学の発展にはいくつかの分水嶺があります。後漢代の張仲景、金元四大家による金元医学、そして明代末から清代にかけて発展した温病学派、これらの医学の発展はよく知られているところです。
本記事の主人公、李東垣は金元四大家の一人です。
金元四大家とは、劉完素、張従正、李東垣、朱丹渓の四人であり、それぞれが構築した医学観から、各医家それぞれに二つ名というべき学派名が冠せられています。劉氏は「寒涼派」、張氏は「攻下派」、李氏は「補土派」、朱氏は「滋陰派」といった具合です。
個人的には、これら学派名で片づけるのではなく、ある程度は各医家の書を通覧しないと彼らの医説を正しく理解できないのでは…???と思います。
李東垣もそのお一人でありまして、「補土派とは脾土・脾胃を補うことを意味する」と解釈されることが多いと感じるのですが、李東垣が重要視した医学観や生命観は、ただ「脾土・脾胃を補う」といったような単純な話ではないと思うのです。
この点については陰火学説に関する論考【陰火学説を素霊難および脈診の観点から考察する】を『中医臨床』165号(Vol.42-No.2)に挙げたとおりです。
本記事では、彼の生きた時代に起こったできごとに目を向けてみましょう。そうすれば「脾胃虚損」「飲食不節」「喜怒憂恐」といった李東垣の言葉もリアルにイメージできるかと思います。
補土派と呼ばれる李東垣
李東垣は12世紀末~13世紀初の人物ですが、現代に生きる私たちは彼が構築した医学の恩恵を受けています。李東垣の功績のひとつ、補中益気湯がそれです。補中益気湯の名を素直に読むと「中焦を補い氣を益す湯液」と読み取れます。しかし李東垣の真意はその先、その奥に含まれていると思います。詳しくは上記【陰火学説を素霊難および脈診の観点から考察する】や補中益気湯や陰火に関する各論文をご参考ください。
いずれにせよ、李東垣がなぜ補土派と呼ばれるほどに補脾胃、補中を重視することになったのか?
その背景を理解する必要があります。
例えば、『内外傷辨惑論』飲食労倦論には、陰火の発生機序において「飲食不節」「喜怒憂恐」「労役過度」といった言葉を用いています。しかし、現代日本人が背景を知らずにこの言葉を読むと、李東垣の真意を理解することはできないだろうと思います。
人は自分の世界・尺度の内で物事を理解しようとする性質があります。伝統医学を学ぶ者としてはこの姿勢・視野は大いに慎むべきでしょう。
李東垣の時代を世界史の視点から見てみよう
では背景を理解するとはどういうことでしょうか?それは李東垣が生きた時代についてある程度知っておくことです。
金元時代という呼称は当時の複雑さをよく表していると思います。
金王朝、元王朝ともに漢民族が治めた王朝ではありません。それまでの中国大陸における主たる王朝は「宋」であり、いわゆる漢民族系王朝でした。それでいて宋は常に北方の民族に圧迫を受けていたという国情があります。
金王朝は女真族による国であり、元王朝はモンゴル人による国であります。ちなみにどちらも世界史用語では征服王朝と呼ばれています。王朝(政府・政治)、民族が複雑にせめぎ合った戦乱の世、それが李東垣の時代といえます。
壬辰の変の舞台となった開封もまた大変な歴史背景を持っています。
1126-1127年に金(女真族)によって開封は占領されます(靖康の変と呼ばれる)。
しかしその約100年後、1230年になると元(モンゴル人)は金への侵攻を再開します。第二代皇帝であるオゴデイ・カアン(オゴタイ・カーン)ーチンギス・カンの第三子にあたる人物ー が南進を再開させたと言われています。
そしてその2年後、本序文に登場する壬辰の年(1232年)に、開封は元軍により包囲され、多くの人が命を落としたと言われています。(下記の書き下し文、下線部分です)
ということで『脾胃論』序に目を通してみましょう。
※画像・本文ともに『脾胃論』より引用させていただきました。
※以下に書き下し文、次いで足立のコメントと原文を紹介。
※現代文に訳さないのは経文の本意を損なう可能性があるためです。口語訳は各自の世界観でお願いします。
脾胃論 序 書き下し文
『脾胃論』序
天の邪氣を感ずるときは則ち、人の五臓を害す。八風の邪、人に中ることの高き者也。
水穀の寒熱を感ずるときは則ち、人の六腑を害する。謂(いわゆる)水穀の胃に入りて、其の精氣上りて肺に注ぎ、腸胃に於いて濁溜す。飲食不節すれば病む者也。
地の湿氣に感ずるときは則ち、人の皮膚筋脈を害す。必ず足より始まる者也。
内経の説く、百病は皆な上中下三者に由り、及び形氣の両虚を論ずる。即ち天地の邪に及ばざれど、乃ち知らんぬ、脾胃の不足、百病の始と為ることを。
有餘不足、世の醫、辯ずること能わざるの者、蓋し已に久し。
往(むかし)者、壬辰の変に遭う、五六十日の間に、飲食労倦の為に、傷る所にて歿する者、将に百万人。皆(みな)謂う傷寒に由りて歿すと。
後に見て之を明かに『内外傷(辨惑論)』及び「飲食労倦傷」の一論を辯じて、而して後に世醫の誤りを知る。学術明らかならずして、人を誤ること乃ち此れを如し。大いに哀れむ可し。之を明かにして既に論を著わす。且つ俗蔽の以て猝悟する可からざるを懼れる也。
故に又『脾胃論』著して之を丁寧す、上は二書の微(微妙)を発し、下は千載の惑を祛(去)る。此の書の果して行われば、壬辰の藥禍、當に従りて作すること無かるべし。仁人の言、其の意(こころ・おもい)愽きこと哉。
己酉七月望月、遺山、元好問 序
本序文が書かれたのは己酉年七月とあり、李東垣生存期間における己酉の年は1249年にあたります。このとき、開封包囲戦(壬辰の変)から17年後のこと。序文を記したのは元好問とあります。元好問という人物は、開封にて李東垣と知り合い、開封から脱出する際に行動を共にしたとのこと(※1)
本序での壬辰の変に関する記述は下線部に当たります。
たった2ヵ月弱の期間で1,000,000人の死者が出た、と元好問は報告しています。しかし、数字の報告だけではその悲惨さをリアルに想像することは難しいものがあります。
同じ壬辰の変に関する記述が『内外傷辨惑論』弁陰証弁陽証に記されています。以下に該当部を抜き出してみましょう。
『内外傷辨惑論』の一部 書き下し文
『内外傷辨惑論』辨陰證陽證
……向者(さきに)壬辰の改元、京師戒厳す、三月下旬に迨(いた)りて、敵を受けること凡そ半月。圍(かこみ)を解くの後、都人の病を受けざる者は万に一二も無し。既に病みて死する者は、踵を継ぎて絶えず。都門は十二か所有り、毎日各門に(死者を)送る所、多き者(ところ)は二千、少なき者(ところ)でも一千を下らず。此れに似た者(状態)が幾三月、此れ百万人。
豈に俱に風寒に感ずる外傷の者ならんや。
大抵、人が圍城の中に在りては、飲食不節し、乃ち勞役に傷る所、言うことを待たずして知るなり。其の朝に飢え暮れに飽き、起居すること時ならず、寒温の所を失するに由る。動(ややもすれば)三両月を経て、胃氣これを虧ること久し。一旦飽食大過して、感じて人を傷る、而して又、調治の宜しきを失す其の死する也。疑うこと無き矣。……
『脾胃論』序の元好問の文章に比べると、『内外傷辨惑論』では壬辰の変の惨状をよりイメージしやすい記述となっています。
李東垣がみた地獄絵図
開封都内の民で病気にならなかった人など10,000人中、1人か2人、ほぼ全員なんらかの健康障害を起こしていたということでしょう。当然、戦災によるものですから軽症のものはカウントされないものとみます。
さらに傷病者が死に至る数は非常に多く、城壁の門から城外・都外に送られる死者の数は毎日1,000-2,000である、と。城門に死者を送るのは、城内に死体を放置しておくとさらなる疫病発生の原因になるからでしょう。そしてその城門は12あると書かれていますので、上記数字(1,000~2,000)のさらに12倍で死者を数える必要があります。
ただ「百万人が死んだ…」と読むのと、上記のように情景をイメージしながら理解するのでは、そのリアルさ切実さが違ってくることでしょう。
さらに世界史の視点から開封攻城戦のようすをみてみましょう。
サイト『世界史の窓』では第二次モンゴル-金戦争の様子を説明してくれています(※2)。1232年(壬辰の年)にモンゴル軍と金軍の間で雌雄を決する戦いが、三峯山(開封の西南)で起こったと解説してくれています。さらにこのサイトでの引用文には以下のようにあります。
(引用)…金の食糧不足は「人口圧」によるものだった。モンゴルの侵攻を恐れた華北の農民が開封に押し寄せ、食糧不足から社会不安が生じていたのである。「開封城内では疫病が発生し、90万以上の棺桶が出たと記録されている。木材の乏しい華北では棺桶は高価であったから、実際に死者は遥かに多いと言われる」
<杉山正明『モンゴル帝国の興亡』上 講談社現代新書 p.61>
この記録内容は『脾胃論』や『内外傷辨惑論』の内容に合致する情報だと思われます。
このようなシビアな当時の世情を理解した上で「飲食不節」「喜怒憂恐」「労役過度」という言葉を理解し直してみましょう。おそらく想定するビジュアル・イメージが大いに変わることだと思います。
「補土派」と呼ばれ、その学派名はややもすれば脾胃を補うだけの“のどかなイメージ”を抱きかねないものを感じます。
単純な補脾胃なら四君子湯(『和剤局方』1107-1110年)でも良いはず。
開封攻城戦という、文字通り“地獄”をみた李東垣が、なぜ補中益気湯を考案したのか?補脾胃に加え、瀉陰火・升陽を組み込んだのは何故か?を考える必要があると思う次第です。
▶李東垣に関する記事
☞ 補中益気湯の立方本旨
☞ 陰火の発生機序を理解するために
☞ 李東垣の生命観ー中気不足から陰火ー
☞ 脾胃論の「凡そ治病、當に其の所便を問うべし」
医学と歴史、医学と政治
伝統医学を勉強していると、医学・医療というものは政治や歴史と密接な関係にある、ということがよく分かります。
人が穏やかに暮らすには衣食住、そして健康が不可欠です。
そして為政者にとって疫病を鎮め、衛生環境を整え、一定水準の医学・医術を完備しておくことは、重要な仕事でした。これらの不安要素を放置すると、反乱がつながる危険性を秘めていたわけです。
医学・医療と国や政治とのつながりは現代でもみることができます。近年のCOVID-19に対する政治や施策をみても大いに納得できることでしょう。
そして見かたを変えると、未来の医学者や学生たちが医学史として現代の我々の仕事ぶりを知ることになることでしょう。
東洋医学部門に関しては、清肺排毒湯や蓮花清瘟㬵嚢などはその名が残るかもしれませんね。
鍼道五経会 足立繁久
■参考資料
※1;真柳誠「『内外傷弁惑論』『脾胃論』『蘭室秘蔵』解題 」『和刻漢籍医書集成』第6輯所収、エンタプライズ、1989年9月(リンク)
※2;第二次モンゴルー金戦争について(リンク)
原文 『脾胃論』序
■原文 『脾胃論』序
天之邪氣感則、害人五臓。八風之邪、中人之高者也。水穀之寒熱感則、害人六腑。謂水穀入胃、其精氣上注於肺、濁溜於腸胃、飲食不節、而病者也。地之濕氣感則、害人皮膚筋脉、必従足始者也。内経説、百病皆由上中下三者、及論形氣両虚、即不及天地之邪、乃知脾胃不足、為百病之始。有餘不足、世醫不能辯之者、蓋已久矣。往者遭壬辰之變、五六十日之間、為飲食勞倦、所傷而歿者、将百萬人。皆謂由傷寒而歿。後見明之、辯内外傷及飲食勞倦傷一論、而後知世醫之誤。学術不明、誤人乃如此。可不大哀耶。明之既著論矣。且懼俗蔽不可以猝悟也。故又著脾胃論丁寧之、上発二書之微、下祛千載之惑。此書果行、壬辰藥禍、當無従而作。仁人之言、其意愽哉。
巳酉七月望月、遺山、元好 問序
詳しい様子を『内外傷辨惑論』に書かれています。
原文 『内外傷辨惑論』の一部
■原文 『内外傷辨惑論』辨陰證陽證
……古人所謂實實虚虚、醫殺之耳。若曰不然、請以衆人之耳聞、目見者、證之。
向者壬辰改元、京師戒厳、迨三月下旬、受敵者凡半月。解圍之後、都人之不受病者、萬無一二。既病而死者、継踵而不絶。都門十有二所、毎月各門所送、多者二千、少者不下一千。似此者幾三月、此百萬人。豈俱感風寒外傷者耶。大抵人在圍城中、飲食不節、乃勞役所傷、不待言而知。由其朝飢暮飽、起居不時、寒温失所。動経三両月、胃氣虧之久矣。一旦飽食大過、感而傷人、而又調治失宜其死也。無疑矣。
非惟大梁為然、遠在真祐與定間、如東平、如太原、如鳳翔、解圍之後、病傷而死。無不然者、余在大梁、凡所親見、有表発者……


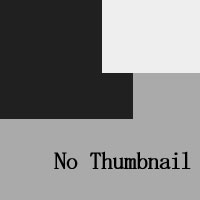











 TOP
TOP