目次
人の身体と世界
人は天地の間に生きる存在であり、天地と人は相応し合っている…という天人相応の思想は、内経の人体観・世界観に強く根ざしている。
経水篇においてもそれは如実にみられ、十二正経を地にある十二の河川に対応させている。
その目的は何か?
天地と相応しているから人の身体は霊妙なるものなのだ!ということが言いたいのではない。
冒頭文にあるように「十二経水なるは、大小・深浅・広狭・遠近ありて、各々同じからず」という、各経脈の特徴を明らかにすることにある。
「十二経は全て同じものではない。」
この点においては、『素問』血氣形志篇第二十四や『霊枢』五味五音篇第六十五、九鍼論第七十八では、三陽経三陰経における氣血の多少について論じられている。(血氣形志と五味五音篇・九鍼論では異なる見解のようであるが、ここでは割愛させていただく)
本篇においても同じように氣血の多少について触れられている。
この各経における氣血の多少が鍼の深浅・灸の壮数に関与するというのだ。
※『霊枢講義』京都大学付属図書館より引用させていただきました。
※以下に書き下し文、次いで足立のコメントと原文を紹介。
※現代文に訳さないのは経文の本意を損なう可能性があるためです。口語訳は各自の世界観でお願いします。
『霊枢』経水第十二
夫れ十二経水なる者、其れ大小・深浅・広狭・遠近ありて、各々同じからず。
五藏六府の高下・小大・穀を受けるの多少も、亦等しからずして相い應ずること、奈何?
夫れ経水なる者、水を受けてこれを行らす。
五藏なる者、神氣魂魄を合してこれを藏す。
六府なる者、穀を受けてこれを行らし、氣を受けてこれを揚ぐ。
経脈なる者、血を受けてこれを營し、合して以って治すること。奈何?
刺の深浅、灸の壮数、得て聞くべき乎?岐伯答えて曰く、善き哉!問い也!
天の至高は度(はか)るべからず、地の至廣は量るべからず、此れこの謂い也。
且つ夫れ人は天地の間、六合の内に於いて生く。
此れ天の高さ、地の廣き也、人力の能く度量して至る所に非ざる也。
若し夫れ八尺の士、皮肉は此れに在りて、外は度量して切循してこれを得るべし、其の死するや解剖してこれを視るべし。
その藏の堅脆、府の大小、穀の多少、脈の長短、血の清濁、氣の多少、
十二経の多血少氣と、その少血多氣と、其の皆多血氣と、其その皆少血氣と、皆大数有り。
其の治、鍼艾を以って、各その経氣を調え、固にその常に合すること有る乎。黄帝曰く、余聞く、耳に快くして、心に解せず。願くば卒かにこれを聞かん。
岐伯答えて曰く、此れ人の天地に参(まじわり)て陰陽に應ずる所以也。
察せずんばあるべからず。足太陽、外は清水に合し、内は膀胱に属して、水道を通ず焉。
足少陽、外は渭水に合し、内は膽に属す。
足陽明、外は海水に合し、内は胃に属す。
足太陰、外は湖水に合し、内は脾に属す。
足少陰、外は汝水に合し、内は腎に属す。
足厥陰、外は澠水に合し、内は肝に属す。
手太陽、外は淮水に合し、内は小腸に属して、水道出づる。
手少陽、外は漯水に合し、内は三焦に属す。
手陽明、外は江水に合し、内は大腸に属す。
手太陰、外は河水に合し、内は肺に属す。
手少陰、外は濟水に合し、内は心に属す。
手心主、外は漳水に合し、内は心包に属す。凡そ此れら五藏六府、十二経水なる者、外に源泉有りて、内に禀る所有り。①
此れ皆 内外相い貫き、環の端の無きが如し、人の経も亦た然り。
故に天は陽を為し、地は陰と為す。
腰以上を天と為し、腰以下を地と為す。
故に海、以北は陰と為し、湖以北は陰中の陰と為す。
漳以南は陽と為し、河以北より漳に至る者は陽中の陰と為す。
漯以南にして江に至る者は陽中の太陽と為す。
此れ一偶の陰陽也。
人と天地の相い参る所以也。黄帝曰く、夫れ経水の経脈に應ずる也、その遠近浅深、水血之多少、各々同じからざる有り、合して以ってこれを刺すこと、奈何?
岐伯答えて曰く、足陽明は五藏六府の海也。
其の脈大にして血多く、氣盛んにして熱壮ん、此れを刺す者は深からざれば散することなく、留めざれば寫さざる也。②
足陽明、刺すこと深さ六分、留めること十呼。
足太陽、(刺すこと)深さ五分、留ること七呼。
足少陽、深さ四分、留ること五呼。
足太陰、深さ三分、留ること四呼。
足少陰、深さ二分、留ること三呼。
足厥陰、深さ一分、留ること二呼。
手の陰陽、其の氣を受けるの道近く、其の氣の来たること疾し、其の刺の深き者は、皆二分を過ぎること無く、其の留ること皆一呼を過ぎること無し。
其の少長・大小・肥痩、心を以ってこれを撩る、命じて天の常に法ると曰う。
これを灸するも亦然り。灸して此れを過ぎる者、悪火を得れば則ち骨は枯れ脈は濇る、刺して此れを過ぎる者は、則ち氣脱す。
黄帝曰く、夫れ経脈の小大、血の多少、廣の厚薄、肉の堅脆及び膕の大小、度量することを為すべき乎。
岐伯答えて曰く、其れ度量を為すべき者、其の中度を取る也。
甚しく脱肉せずして血氣衰えざる也。
若し夫れ人の痟痩を度りて形肉脱する者は、悪んぞ以って度量して刺すべき乎。
審らかに切循捫按して、寒温盛衰を視てこれを調う、是れ謂る是、適に因りて之を眞と為す也。
経水篇のみどころ
十二経脈は外に十二経水と合して(相応して)、内は五臓六腑に属すとある。
前篇の経別では十二経が六合を形成することで天地と人体の相い応じる様を表現していたが、
本篇の経水では、十二経脈と十二経水との相応を提示し、人と天地が相参することを説いている。
①五藏六府、十二経水、外に源泉あり内に禀けるところあり
『臓腑経絡システムというのは実にうまくできている…』と思わず唸らされる文である。
正経にとって臓腑は属絡の対象であり、経氣の供給源でもあるとイメージしている。
しかしこの文からは、経脈は「源泉」であるとも解釈できるのではないか?と思ってしまう。
この点、井榮兪経合の性質を説く『霊枢』本輸篇の記載にも通ずるものがある。
経脈とは正気を与えられ循らすだけの受動的な存在ではないと再認識できる文であり、
経脈の調整を主とする鍼灸の可能性を感じさせられるばかりである。
②多氣多血に鍼刺は深く留めること
具体的な刺法について言及されている箇所である。
陽明は多氣多血、これは血氣形志篇、五味五音篇、九鍼論の共通の観点である。
この多氣多血である故に、邪が侵入することで起こる熱化も甚しい。
この病態に対し、鍼刺は深く、且つ留めなければ、邪を散ずる寫すことができないという。
この刺法を理解するには、他篇の記述と併せて要考察である。
また、他経の鍼刺の深・留についてであるが、比較のため以下に列挙しておく。
足陽明(多血多氣)深六分、留十呼
足太陽(多血少氣)深五分、留七呼。
足少陽(多氣少血)深四分、留五呼。
足太陰(多血少氣)深三分、留四呼。
足少陰(多氣少血)深二分、留三呼。
足厥陰(多氣少血)深一分、留二呼。
※『霊枢』五味五音篇、九鍼論の説を採用している。
但し、単純な三陽三陰と氣血多少の分類ではないことは、
手の三陽経三陰経と足六経とを明確に区分していることからも明白である。
手の経は、陽気を受けること近く、氣の来たることも亦疾い。
そのため鍼刺は、二分を過ぎることは無く、留鍼することも一呼を過ぎることが無いという。
氣の動きが早く、経も足のそれに比べて短い。
その分、繊細な氣の調整を要するということであろうか。
『霊枢』経水第十二
夫十二経水者、其有大小深浅広狭遠近、各不同。
五藏六府之高下小大受穀之多少、亦不等相應、奈何?
夫経水者、受水而行之。
五藏者、合神氣魂魄而藏之。
六府者、受穀而行之、受氣而揚之。
経脈者、受血而營之、合而以治。奈何?
刺之深浅、灸之壮数、可得聞乎?岐伯答曰、善哉!問也!
天至高不可度、地至廣不可量、此之謂也。
且夫人生於天地之間、六合之内、此天之高、地之廣也。非人力之所能度量而至也。
若夫八尺之士、皮肉在此、外可度量切循而得之、其死可解剖而視之。
其藏之堅脆、府之大小、穀之多少、脈之長短、血之清濁、氣之多少、
十二経之多血少氣、與其少血多氣、與其皆多血氣、與其皆少血氣、皆有大数。
其治以鍼艾、各調其経氣、固其常有合乎。黄帝曰、余聞之快於耳、不解於心、願卒聞之。
岐伯答曰、此人之所以参天地而應陰陽也。不可不察。
足太陽、外合於清水、内属於膀胱、而通水道焉。
足少陽、外合於渭水、内属於膽。
足陽明、外合於海水、内属於胃。
足太陰、外合於湖水、内属於脾。
足少陰、外合於汝水、内属於腎。
足厥陰、外合於澠水、内属於肝。
手太陽、外合於淮水、内属於小腸、而水道出焉。
手少陽、外合於漯水、内属於三焦。
手陽明、外合於江水、内属於大腸。
手太陰、外合於河水、内属於肺。
手少陰、外合於濟水、内属於心。
手心主、外合於漳水、内属於心包。
凡此五藏六府十二経水者、外有源泉、而内有所稟。此皆内外相貫、如環無端、人経亦然。
故天為陽、地為陰。腰以上為天、腰以下為地。
故海以北者為陰、湖以北者為陰中之陰。
漳以南者為陽、河以北至漳者為陽中之陰。漯以南至江者為陽中之太陽、此一偶之陰陽也。所以人與天地相参也。黄帝曰、夫経水之應経脈也。其遠近浅深、水血之多少、各有不同、合而以刺之、奈何?
岐伯答曰、足陽明、五藏六府之海也。其脈大血多、氣盛熱壮、刺此者不深弗散、不留不寫也。
足陽明、刺深六分、留十呼。
足太陽、深五分、留七呼。
足少陽、深四分、留五呼。
足太陽、深三分、留四呼。
足太陰、深三分、留四呼。
足少陰、深二分、留三呼。
足厥陰、深一分、留二呼。手之陰陽、其受氣之道近、其氣之来疾、其刺深者、皆無過二分、其留皆無過一呼。
其少長大小肥痩、以心撩之、命曰法之天常。
灸之亦然。灸而過此者、得悪火則骨枯脈濇、刺而過此者、則脱氣。
黄帝曰、夫経脈之小大、血之多少、廣之厚薄、肉之堅脆及膕之大小、可為度量乎。
岐伯答曰、其可為度量者、取其中度也。
不甚脱肉而血氣不衰也。若夫度之人、痟痩而形肉脱者、悪可以度量刺乎。
審切循捫按、視寒温盛衰而調之、是謂因是適而為之眞也。
鍼道五経会 足立繁久
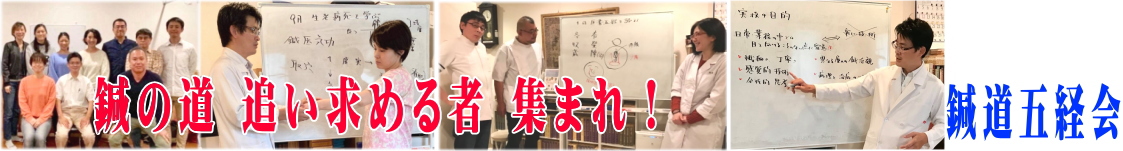



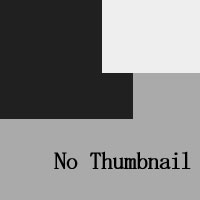









.jpg?fit=120%2C80)










 TOP
TOP