目次
はじめに
鍼道五経会の流儀のひとつに「鍼法と診法の一致」すなわち【診鍼一致】【診鍼一貫】がある。
過去に『医道の日本』6月号ではそのような趣旨の投稿をさせていただいた。
「診鍼一致」を分かりやすく伝えるために、鍼灸師を衛気タイプ、営気タイプ、血タイプなどと分類したが、決してオモシロおかしく書いたのではない。
その根拠には『素問』『霊枢』がある。
衛気・営気を理解する元となった論篇を「霊枢から学ぶ鍼と氣」というシリーズで紹介しようと思う。
気に関する部位のみ、個人的な判断で引用しているため、全論全篇の文章ではない点もあるがご容赦いただきたい。
※『霊枢講義』京都大学付属図書館より引用させていただきました。
※以下に書き下し文、次いで原文を紹介。
※現代文に訳さないのは経文の本意を損なう可能性があるためです。口語訳は各自の世界観でお願いします。
『霊枢』九鍼十二原第一
九鍼十二原第一 法天(『甲乙経』巻五 、『太素』巻二十一 九鍼要道、九鍼要解、諸原所生、『類經』巻八 経絡類 14井榮兪経合数 15十二原、巻二十二 52久病可刺 53刺諸病諸痛)
黄帝、岐伯に問うて曰く、余、萬民を子とし、百姓を養いて、其祖税を収む
・・・(略)・・・
微鍼を以ってその経脈を通じ、その血氣を調え、その逆順出入の會(会)を営して、後世に伝えうべからしめんことを欲す。
・・・(略)・・・
岐伯答て曰く、臣請う 推してこれを次にし、綱紀有らしめ、一に於いて始まり、九に於いて終らん。
請うその道を其わん。
小鍼の要とは、陳べ易く入り難し。
粗(粗工)は形を守り、上(上工)は神を守る。
神乎神、客 門に在りて、未だその疾を観ず、悪(いずくん)ぞその原を知らん。
刺の微、速遅に在り。
粗は関を守り、上は機を守る。
機の動、その空中を離れず。空中の機とは、清浄にして微。
その来るに逢うべからず、その往を追うべからず。
機の道を知る者、髪を以って掛かるべからず、機の道を知らざるは、これを叩くも発せず。
その往来を知りて、要、これと期す。粗の闇なる乎、妙なる哉!
工独りこれ有り。
往く者を逆と為し、来たる者を順と為す。
明に逆順を知りて、正行して問うこと無し。
迎いてこれを奪う、悪んぞ虚無きを得ん。
追いてこれを濟う、悪んぞ實無きを得ん。
これを迎え、これに随い、意を以てこれを和す、鍼道畢ぬ。凡そ鍼を用いる者、
虚すれば則ちこれを實し、満すれば則ちこれを泄す、
宛陳すれば則ちこれを除き、邪勝てば則ちこれを虚にす。大要に曰く、
徐にして疾きときは則ち實す、疾くして徐なるときは則ち虚す。
言う、實と虚は、有るが若く無きが若く。
後と先を察して、亡きが若く存するが若く、
虚と為し實と為し、得るが若く失うが若し。
虚實の要は、九鍼の最妙なり。
補寫の時、鍼を以てこれを為す。寫は曰く、必ず持ちてこれを内(い)れ、放ちてこれを出す。
陽を排して鍼を得、邪氣は泄することを得る。
按じて鍼を引く、是を内温と謂う、血散ずることを得ず、氣出づるを得ざる也。
補は曰く、これに隨う、これに隨うの意、これを妄する若し、行くが若く、按ずる若く、
蚊虻の止まるが如く、留るが如く還るが如く、去ること弦絶するが如し。
左をして右に属せしむ。その氣故に止まる、外門已に閉じ、中氣乃ち實す。
必ず留血させること無く、急に取りてこれを誅せよ。鍼を持つの道、堅きことを宝と為す。
指を正し直に刺し、左右に鍼無し。
神は秋毫に在り、意を病者に属し、審かに血脈を視る者、これを刺して殆きこと無し。
方(まさ)に刺の時、必ず懸陽及び両衛とに在り。(衛の字は、『甲乙』では衡、校正では衝に作す)
神は属して去る勿れ、病の存亡を知り
血脈は、腧に在りて横居す、これを視て独り澄み、これを切して独り堅し。
・・・(九鍼については「九鍼」にて詳述)・・・
夫れ氣の脈に在る也、邪氣上に在り、濁氣は中に在り、清氣は下に在る。
故に陥脈に鍼すれば則ち邪氣出づ、中脈に鍼すれば則ち濁氣出づ、大い深く鍼すれば則ち邪氣反って沈み、病益す。
故に曰く、皮肉筋脈に各々處する所有り、病に各々宜しき所有り、各々形同じからず。
各々以ってその宜しき所に任ず。
實無く虚無く、不足損して有餘を益すれば、これ甚病と謂う、病益々甚し。
五脈を取る者は死し、三脈取る者は恇れる。
奪陰する者は死し、奪陽する者は狂する。
鍼道畢ぬ。これを刺して氣至らざれば、その数を問うこと無し。
これを刺して氣至れば、乃ちこれを去りて復た鍼する勿れ。
鍼に各々宜しき所有り、各々形同じからず、各々その為す所に任ず。
刺の要、氣至りて効有り。
効の信、風の雲を吹くが若し。
明なるかな蒼天を見るが若し。
刺の道畢んぬ。黄帝曰く、願くば聞かん、五藏六府の出る所の處を。
岐伯曰く、五藏五腧、五五二十五腧、六府六腧、六六三十六腧。
経脈十二、絡脈十五、凡て二十七氣、以って上下す。出る所を井と為し、溜る所を榮と為し、注ぐ所を兪と為し、行く所を経と為し、入る所を合と為す。
二十七氣の行く所、皆五輸に在る也。
筋の交、三百六十五会。その要を知る者は、一言にして終る。
その要を知らざるは、流散して窮まること無し。
節と言う所は、神氣の遊行し出入する所也。皮肉筋骨に非ざる也。
その色を観て、その目を察し、その散復を知り、その形を一にし、その動静を聴き、その邪正を知る。
右はこれを推すことを主り、左は持ちてこれを禦する、氣至りてこれを去る。
凡そ将に鍼を用いんとするは、必ず先ず脈を診て、氣の劇易を視て、乃ち以って治すべき也。
五藏の氣、已に内に於いて絶するに、鍼を用いる者、反ってその外を實すれば、これを重竭と謂う。
重竭すれば必ず死す。その死するは静なり。
これを治する者、輒ちその氣に反して、腋と膺を取る。
五藏の氣、已に外に於いて絶するに、鍼を用いる者、反ってその内を實すれば、これを厥逆と謂う。
厥すれば則ち必ず死ず。その死するは躁なり。
これを治する者、反って四末を取る。
刺の害、中りて去らざれば則ち精泄れる、中を害して去れば則ち氣を致す、精泄れるときは則ち病益々甚しく恇れる。氣を致せば則ち生じて癰瘍と為す。
五藏に六府有り、六府に十二原有り、十二原は四関に於いて出づる。四関は五藏を主治す。五藏に疾有れば、當に十二原を取るべし。
十二原は五藏がこれ三百六十五節の氣味を禀ける所以也。五藏に疾有るや、應は十二原に出づる、十二原各々出づる所有り、明らかに其の原を知り、其の應を観て知五藏の害を知るなり。
陽中之少陰、肺也。其原出於太淵、太淵二。
陽中之太陽、心也。其原出於大陵。大陵二。
陰中之少陽、肝也。其原出於太衝、太衝二。
陰中之至陰、脾也。其原出於太白、太白二。
陰中之太陰、腎也。其原出於太渓、太渓二。
膏之原出於鳩尾一。肓之原出於脖胦、脖胦一。
凡そ此れら十二原は、五藏六府の疾を有る者を主治する也。
脹は三陽を取り、飧泄は三陰を取る。
今、夫れ五藏六府の疾有る也、譬えば猶(なお)刺の如き也、猶汚れの如き也、猶結の如き也、猶閇の如き也。
刺すること久しと雖も、猶(なお)抜くべきが如く也。
汚れ久しきと雖も、猶雪(そそぐ)べきが如く也。
結ぼれ久しきと雖も、猶解くべきが如く也。
閇たること久しと雖も、猶決すべきが如き也。
或いは言う、久疾の取る可からざる者は、其の説に非ざる也。
夫れ善く鍼を用いる者は、其の疾を取るや、猶(なお)刺を抜くが如き也、猶汚れを雪(そそぐ)が如き也、猶結ぼれを解くが如き也、猶閇るを決するが如く也。疾の久しきと雖も、猶畢する可き如く也。
治す可からずと言う者は、未だ其の術を得ざる也。
諸々の熱を刺す者、手を以て湯を探るが如くし、
寒清を刺す者は、人の行くを欲せざるが如くせよ。
陰に陽疾の有る者は、之を下陵の三里に取る、正しく往れば殆(あやうき)こと無し。氣下りて乃ち止む、下らざれば複た始むる也。
疾高くして内なる者は、之を陰之陵泉に取る。
疾高くして外なる者は、之を陽之陵泉に取る也。
初めて霊枢の九鍼十二原を読んだときの感想は『なんのことやらチンプンカンプン…』であった。
一旦『黄帝内経』から離れて『傷寒雑病論』に入り、そこから『難経』を経由して『素問』『霊枢』に戻る…という古典文献の学び方をしている。回り道をというか王道ではない学び方をしているなという自覚はある。しかし自分にとってはそれで良かったのかもしれない。
さて今回の『霊枢から学ぶ鍼と氣』の目的はあくまでも「衛気と営気をはじめとする諸氣の概念を理解する」こと、そして「衛気と営気を理解した上で診法と鍼法を理解する」ことにある。
その都合上、失礼を承知で随所に省略箇所がある。
本篇には衛気と営気に関する直接的な記述はみられないが、無視することのできない有名なフレーズが随所にある。
粗工は形を守り、上工は神を守る
「粗工は形を守り、上工は神を守る。」「粗工は関を守り、上工は機を守る」
粗工とはレベルの低い術者、上工はハイレベルな術者として使われるが、単にランク分けではなく、成長過程として読んでみるのも良いだろう。
形を守る段階から始まり、神(気・血・精・神)を守る段階へと至るという解釈も面白いかもしれない。
また別の観点から「上工守神」を考察する必要もある。
鍼と神、といえば『素問』宝命全形論第二十五、八正神明論第二十六を思い浮かべる人は多いであろう。また同じ『霊枢』にも随所に神は散見されるが、本神篇第八や終始篇第九も知っておくべきだ。
宝命全形論では鍼治の法として「一に曰く治神、二に曰く養身を知る、三に曰く毒薬の真為ることを知る、四に曰く砭石の小大を制す、五に曰く、府藏血氣の診を知る」とあり、神を治める治神は鍼師が修めるべき至上の命題という位置づけにある。
同様に『霊枢』本神篇では「凡そ刺之法、必ず先に神を本とす」とあり、やはり鍼法刺法の大前提に神がある。
では神とは何ぞや?
八正神明論では黄帝が同じ質問を岐伯に問いかけている。
「神と何ぞや?」と。
この問いに岐伯は次のように答えている。
「神なるかな神は、耳に聞こえず、目に明かに心開けて志先に、慧然として獨悟す、口には言うこと能わず、倶に視て獨見す、適に昏するが若し、昭然として獨明なり、風の雲を吹くが若し、故に曰く、神と。」
一見したところ『結局、何を言っているのか分からない…』と思えるが、この答えを聞いて納得した黄帝さまはやはり利発な方なのだ。さすが数々のレジェンドを残した人物である。
この八正神明論は「粗工守形、上工守神」と同じで、形と神との対比である。そのため、岐伯のこの説明は非常に微に入り細を穿つような解説だといえる。
しかし分からない人にとってはどれだけ詳細に説明されても、分からないものは分からない。むしろ余計に混乱してしまうものである。
もう少しイメージしやすい神の説明に終始篇の一節を紹介しよう。
「凡そ刺の法とは、…(中略)…深くに居し静かに處して、神の往来を占う。戸を閉じて牅を塞ぎ、魂魄散ぜず、意を専にし神を一にす。精氣の分は、人の声を聞くことなかれ、以ってその精を収め、必ずその神を一にして、志をして鍼に在らしむ。浅してこれを留め、微にしてこれを浮し、以ってその神を移す、氣至りて乃ち休す。…」
実際に鍼を行う際の情景が目に浮かぶような説明である。
この説明では「神を一にする(専意一神)(必一其神)」というフレーズに注目したい。“一にする”ということは神とは“複数ある”か、もしくは“分散している”か、ということであろう。
かといって“散漫となっている精神を集中すべし”という解釈では芸がない。鍼する際に集中しない鍼師などいないのだから(より高度な集中の段階は除いて)。
この文では「神」「魂」「魄」「意」「精」「神」「志」そして「気」という言葉・概念を用いて、上工の鍼がいかに高次であるかを説いている。(詳しくは終始篇第九を参照のこと)
粗工は形を守り、上工は機を守る
また上工が守る機についてであるが、
「機の動とは空中を離れず」、「空中の機とは清浄にして微」とあり、
機の動とは“空中”と見えない無形の要素に関わるものである。
そもそも「機」という字は機織りのことを指す。加えて複雑なからくりをも表わす言葉を意味する。
ここから考えるに「上工は機を守る」とは複雑な事象の中に見え隠れする“兆し”、これを重視するのが上工である…というメッセージのように受け取れる。
機という有形のもの(機械)を表わしつつも、有形の背後に隠れる無形のもの(兆しや動き)を含む文字を用いた意味はここにあるのではないだろうか?単に兆しや変化を伝えるだけであれば「機」ではなく「時」や「化」といった文字で十分だったはずだと思えるのだ。
同様に考えると、粗工は「関」を大事する…の意味も見えてくる。
「関」とは門を閉ざす閂(かんぬき)である。「機」と同じく有形の物を表わす文字であり「停止」を意味する言葉である。
つまり上工は目に見えぬ「時」や「兆し」「変化」を重視して鍼する。粗工は固定された状態、止まった物に対して鍼をする。
もちろん上達の一過程として、粗工の形の段階から入るのが望ましいが、さらなる上の段階があるということを見据えて精進すべきであろう。
ちなみにこの「機」の考えは鍼道五経会の脈診における脈機に応用されている。
邪気と濁気と清気
「夫れ氣の脈に在る也、邪氣上に在り、濁氣は中に在り、清氣は下に在る。」の言葉から、
脈(経脈)は層構造であることが分かる。
清濁は営衛生会篇第十八にある「清なる者を営と為し、濁なる者を衛と為す。(清者為営、濁者為衛)」のことであろう。
清なる者を営と為し、濁なる者を衛と為す。
水穀の清氣である営は脈中に在り、水穀の悍氣である衛は脈外に在るため、清氣は下にあり、濁氣はその上にある。(外襲の邪に限定するが)邪氣は外より来るため、結果として最も表層に位置することになる。と、このように考えるとこの層構造はイメージしやすい。
なにより経脈が復層構造であることを理解することで、鍼治療がより複雑なものとなる。
鍼を刺せば終わりという簡単なものではない。
経穴という座標に深さ・層という要素を加えて3次元となる。
実際には、3次元のポイントに鍼を至らせてから、
さらに鍼尖(もしくは鍼体)を起点としたベクトルを意識するので、より多次元の鍼治を考慮する必要がある。
鍼の本数
「これを刺して氣至らざれば、その数を問うこと無し」とあるように、
鍼の本数を決定するのは、気至か気不至かである。
気が動かなければ、鍼の数を問わずさらに鍼せよ、とある。
「数を問わず鍼を刺す=オーバー・ドーゼ」とみてしまいがちである。
しかし、そもそもドーゼとは「薬などの投与量」の意である。
そして気至るとは、体の反応・リスポンスである。
気不至=反応がなければ、それはドーゼが足りていないのである。
では何をもって適正な刺激量なのか?
それは鍼の本数ではなく、気の至り(気至)である。
ちなみに得気(酸・重・鈍・麻)と気至は別物である。
気至か気不至かをどう見分けるのか?
如実にその反応が現れるのが、脈である。
脈は気と血が流れる部位である故に、鍼刺の前後で脈を診ることが肝要となるのである。
気至か気不至かを確認するには、やはり脈を診ることが確かなのである。
神や機を守る上工としては、脈を診ることは重要である。
後代の「脈に神有るを貴ぶ」という言葉にもつながってくると言えるだろう。
この脈と気の密接な関係については、以降の論篇にて詳解しようと思う。
節とは神気の遊行出入する所
節とは、神氣の遊行し出入する所也。皮肉筋骨に非ざる也。
これは節のみならず、経穴という言葉に置き換えてもよいだろう。(『素問』離合真邪論第二十七の神氣の記載、『霊枢』小鍼解第三の記載からこのように考える。)
経穴を通じて、神気が出入しているのだ。
そして「筋の交、三百六十五会」とあり、このようなポイントが365ヶ所ある。
この数字から、天人相応の思想が見えてくる。
つまり経穴は単なる治療ポイントではないのだ。
この文から古代中国における人体観、自然観がうかがい知ることができよう。
下には『霊枢』九鍼十二原の原文(該当箇所)を引用している。
原文『霊枢』九鍼十二原第一 法天
欲以微鍼通其経脈、調其血氣、營其逆順出入之會。令可傳於後世・・・岐伯答曰、臣請推而次之、令有綱紀、始於一、終於九焉。請言其道。
小鍼之要、易陳而難入。
粗守形。上守神。
神乎神、客在門。
未観其疾、悪知其原?
刺之微、在速遅。粗守関、上守機。
機之動、不離其空中。空中之機、清浄而微。
其来不可逢、其往不可追。知機之道者、不可掛以髪、不知機道、叩之不発。
知其往来、要與之期。
粗之闇乎、妙哉!工獨有之。
往者為逆、来者為順。明知逆順、正行無問。迎而奪之、悪得無虚。追而濟之、悪得無實。
迎之随之、以意和之、鍼道畢矣。凡用鍼者、虚則實之、満則泄之、宛陳則除之、邪勝則虚之。
大要曰、徐而疾則實、疾而徐則虚。
言實與虚、若有若無。
察後與先、若亡若存、為虚為實、若得若失。
虚實之要、九鍼最妙。補寫之時、以鍼為之。
寫曰、必持内之、放而出之、排陽得鍼、邪氣得泄。
按而引鍼、是謂内温、血不得散、氣不得出也。
補曰隨之、隨之意、若妄之、若行若按、如蚊虻止、如留如還、去如弦絶。
令左属右、其氣故止、外門已閉、中氣乃實。
必無留血、急取誅之。
持鍼之道、堅者為寶、正指直刺、無鍼左右。
神在秋毫、属意病者、審視血脈者、刺之無殆。
方刺之時、必在懸陽及與両衛。(衛の字は、『甲乙』では衡、校正では衝に作す)
神属勿去、知病存亡。
血脈者、在腧横居、視之獨澄、切之獨堅。
・・・(九鍼については「九鍼」にて詳述)・・・
夫氣之在脈也、邪氣在上、濁氣在中、清氣在下。
故鍼陥脉則邪氣出、鍼中脉則濁氣出、鍼大深則邪氣反沈、病益。
故曰、皮肉筋脉各有所處、病各有所宜、各不同形、各以任其所宜。
無實無虚、損不足而益有餘、是謂甚病、病益甚。
取五脉者死、取三脉者恇。
奪陰者死、奪陽者狂。
鍼道畢矣。
刺之而氣不至、無問其数。刺之而氣至、乃去之勿復鍼。
鍼各有所宜、各不同形、各任其所為。
刺之要、氣至而有効。
効之信、若風之吹雲、明乎若見蒼天。刺之道畢矣。
黄帝曰、願聞五藏六府所出之處。
岐伯曰、五藏五腧、五五二十五腧、六府六腧、六六三十六腧。
経脈十二、絡脈十五、凡二十七氣以上下。
所出為井、所溜為榮、所注為兪、所行為経、所入為合。
二十七氣所行、皆在五輸也。筋之交三百六十五會。知其要者、一言而終、不知其要、流散無窮。
所言節者、神氣之所遊行出入也。非皮肉筋骨也。
観其色、察其目、知其散復、一其形、聴其動静、知其邪正。右主推之、左持而禦之、氣至而去之。
凡将用鍼、必先診脈、視氣之劇易、乃可以治也。
五藏之氣、已絶於内、而用鍼者、反實其外、是謂重竭。重竭必死、其死也静。治之者、輒反其氣、取腋與膺。
五藏之氣、已絶於外、而用鍼者、反實其内、是謂厥逆。厥則必死、其死也躁。治之者、反取四末。
刺之害、中而不去、則精泄、害中而去、則致氣、精泄則病益甚而恇、致氣則生為癰瘍。五藏有六府、六府有十二原、十二原出於四關、四關主治五藏、五藏有疾、當取十二原。
十二原者、五藏之所以禀三百六十五節氣味也。 五藏有疾也、應出十二原、十二原各有所出、明知其原、観其應而知五藏之害矣。
陽中之少陰、肺也。其原出於太淵、太淵二。
陽中之太陽、心也。其原出於大陵。大陵二。
陰中之少陽、肝也。其原出於太衝、太衝二。
陰中之至陰、脾也。其原出於太白、太白二。
陰中之太陰、腎也。其原出於太渓、太渓二。
膏之原出於鳩尾一。肓之原出於脖胦、脖胦一。
凡此十二原者、主治五藏六府之有疾者也。
脹取三陽、飧泄取三陰。
今夫五藏六府之有疾也、譬猶刺也、猶汚也、猶結也、猶閇也。刺雖久、猶可抜也。汚雖久、猶可雪也。結雖久、猶可解也。閇雖久、猶可決也。或言久疾之不可取者、非其説也。
夫善用鍼者、取其疾也、猶抜刺也、猶雪汚也、猶解結也、猶決閇也。疾雖久、猶可畢也。言不可治者、未得其術也。
刺諸熱者、如以手探湯。
刺寒清者、如人不欲行。
陰有陽疾者、取之下陵三里、正往無殆。氣下乃止、不下複始也。
疾高而内者、取之陰之陵泉。疾高而外者、取之陽之陵泉也。
鍼道五経会 足立繁久

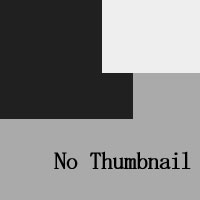

.jpg?fit=120%2C80)






















 TOP
TOP