目次
霊枢 脹論第三十五のみどころ
脹論にも衛気と営気に関する記載がある。脹という病名から浮腫や腫れなど“水”を主体とする病にもみえる。しかし本文文脈から察するに、どうも水の病ではないようである。氣分における陰陽、すなわち衛気と営気の関係をいかに理解するか?が、本篇脹論を理解する手掛かりになるだろうと考えている。
それでは本文を読みすすめてみよう。
※『霊枢講義』京都大学付属図書館より引用させていただきました。
※以下に書き下し文、次いで足立のコメントと原文を紹介。
※現代文に訳さないのは経文の本意を損なう可能性があるためです。口語訳は各自の世界観でお願いします。
霊枢 脹論第三十五
書き下し文・霊枢脹論第三十五(『甲乙経』巻八 五藏六府脹、『太素』巻二十九 脹論、『類経』巻十六 疾病類 56 臓腑諸脹)
黄帝曰く、脈の応、寸口に於いて、如何にして脹するか?
岐伯曰く、その脈の大堅にて以て濇なる者は、脹也①。
黄帝曰く、何を以て臓腑の脹を知る也?
岐伯曰く、陰は臓を為し、陽は腑を為す。
黄帝曰く、夫れ氣の人をして脹らしむる也、血脈の中に在るか、臓腑の内か。
岐伯曰く、三者(一に云う“二”字)、皆存するなり。然れども脹の舎には非ざる也。
黄帝曰く、願くば脹の舎を聞かん。
岐伯曰く、夫れ脹たる者、皆な臓腑の外に在り、臓腑を排して胸脇を郭とし皮膚を脹る、故に命じて脹と曰う。
黄帝曰、臓腑の胸脇・腹裏の内に在る也、匣匱(こうき)の禁器を藏するが若き也、各々次舎有り、名を異にして処を同じくす。一域の中、其の氣は各々異なる。願くば其の故を聞かん。
黄帝曰く、未だ其の意を解せず、再び問わん。
岐伯曰く、夫れ胸腹は、臓腑の郭也。
膻中なる者は、心主の宮城也。
胃は大倉也。
咽喉小腸は、伝送也。
胃の五竅は、閭里門戸也。
廉泉玉英は、津液の道也。
故に五臓六腑は、各々に畔界(はんかい)あり。其の病は各々に形状有り。
営気は脈を循り、衛気は逆すれば、脈脹を為す。衛氣が脈に並び分を循れば、膚脹を為す②。
三里にして寫する。近き者は一下し、遠き者は三下する。虚実を問うこと無かれ、工は疾く寫するに在り。
黄帝曰く、願くば脹形を聞かん。
岐伯曰く、夫れ心脹は、煩心し短氣し、臥して安からず。
肺脹は、虚満して喘欬す。
肝脹は、脇下満して痛みは小腹に引く。
脾脹は、善く噦し、四肢煩悗し、体重く、衣に勝つこと能わず、臥して安からず。
腎脹は、腹満して背に引き、央央然として腰髀痛む。
六府の脹、胃脹は腹満して、胃脘痛み、鼻は焦臭を聞きて食を妨げ、大便難し。
大腸脹は、腸鳴して痛み濯濯たり、冬日に寒に重感すれば則ち飧泄して化せず。
小腸脹は、少腹瞋脹し腰に引きて痛む。
膀胱脹は、少腹満して氣癃す。
三焦脹は、氣、皮膚中に満ち、軽軽然として堅からず。
胆脹は、脇下痛み脹れ、口中苦く、善く太息す。
凡そ此れら諸脹は、其の道は一に在り、明らかに逆順を知れば、鍼数は失わず。
虚を瀉し実を補せば、神は其の室を去り、邪を致し正を失えば、真は定むるべからず。粗(粗工)の敗るる所、之を夭命と謂う。
虚を補う実を瀉すれば、神は其の室に帰し、久しく其の空を塞ぐ、之を良工と謂う。
黄帝曰く、脹は焉(いずくに)生じ、何に因りて有るか?
岐伯曰く、衛気の身に在る也、常然として脈に並び、分肉を循る。(衛気の)行りに逆順有り、陰陽相随い、乃ち天和を得る③。五臓は更々始まり、四時に序有りて、五穀は乃ち化する。然る後に厥氣は下に在れば、営衛は留止し、寒気は逆上す、真邪相い攻め、両の氣は相い搏ちて、乃ち合して脹を為す也。
黄帝曰く、善し。何を以て惑いを解かん。
岐伯曰く、之を真に於いて合し、三合而して得る。
帝曰く、善し。
黄帝、岐伯に問うて曰く、脹論に言う、虚実を問うこと無かれ、工は疾く寫することに在り、近き者は一下し、遠き者は三下す。今、其の三(下)して下らざること有る者、其の過は焉(いずく)に在るか?
岐伯対えて曰く、此れ肉肓に陥って而して氣穴に中る者を言う也。氣穴に中らざれば、則ち氣は内に閉づ。鍼は肓(肉肓)に陥らずときは則ち氣は行らず。上越して肉に中れば、則ち衛気は相い乱れ、陰陽相い逐う④。其れ脹に於ける也、當に寫すべし、寫さざれば、氣は故に下らず。三にして下らざれば、必ず其の道を更(あらた)む。氣下りて乃ち止む、下らざれば復た始む、以て万全たるべし。
烏(いずくん)ぞ殆(あやう)き者有らんか。
其れ脹に於ける也、必ず其の𦙳(しん)を審らかにし、當に寫すべきに則ち寫し、當に補するべきに則ち補す、鼓の桴に応ずるが如く、悪(いずくん)ぞ下らざる者の有らん乎。
脈診情報から脹の病態を知る
本篇にある唯一の脈証「その脈の大堅にて以て濇なる者は、脹也(其脉大堅以濇者、脹也。)」(下線部①)には、“脹”の性質が記されている。
正確な解釈ではないかもしれないが、以下に「脹」の病態を『診家枢要』の脈理を基とした考察(あくまでも私見として)を載せておく。
さて「其脈大堅以濇」という情報には脹の病態が示唆されている。
歴代の医家たち(といっても、以下に挙げるのは馬氏・張氏の引用のみであるが)は次のように述べている。
馬蒔
「…其脉大者、以邪氣有餘也。其脉堅者、以邪氣不散也。其脉澀者、以氣血澀滞也。故爲脹。」
張景岳
「脉大者、邪之盛也。脉堅者、邪之實也。澀因氣血之虚而不能流利也。大都洪大之脉、陰氣必衰、堅强之脉、胃氣必損、故大堅以澀、則病當爲脹。」
もちろん上記の註文に不満はないが、せっかくなのでもう少し考察を進めてみよう。
大脈が示す情報
脈大とは「陽性の亢進」を示す脈である。
『診家枢要』には「血虚して氣は相い入ること能わざる也(血虚氣不能相入也)」ここでは血と氣を陰陽の対比として記しているが、陽分が陰分に入り交流することができなくなった(もしくはそのような状態になりつつある)ことを示す脈である。
しかし脹の病態を解するには、上記引用文の解釈を「血」を陰分・営氣営分として読みかえても良いだろう。
陰分・営分の不足により、陽が更新し、氣分における陰陽交流に不調を起こす…という病態として読み取ることができる。
ここで細かな説明を加えておくが、“血虚≒陰分・営分の虚”として解するも“血(≒陰分)そのものが虚しているのではない”ということに注意すべきである。もし本当に血虚(≒陰分虚)であれば、そもそも大脈にはなり得ないからだ。
血虚(≒陰分虚)を強いて言い換えるならば、“陰分の氣が虚する状態”と解すべきであろう。陰分の氣が不足すれば、相対的に陽分の氣が旺盛となる。気分における陰陽差とも言い換えることができよう。
このように理解することで大脈の形状や感触もよりリアルに脳内に描くことができるのだ。
『診家枢要』脈大より
浮にてこれを取れば浮にして洪なるが若し、沈めてこれを取れば大にして無力。
血虚し気 相入れること能わざる也。
経に曰く、大なるは病進と為す。
■原文
浮取之若浮而洪、沈取之大而無力。
為血虚氣不能相入也。経曰、大為病進。。
また、この氣分における陰陽不和の原因を推し測れば、中氣(胃氣)の機能不全として解することができる。
中氣とは陰と陽をつなぐ存在である故、これを胃氣と言い換えることができる。『列子』でいう冲和(沖和)の氣ともいえよう。この胃氣のはたらきが不全となり、陰陽不和となった状態を、脈堅が示す病態として解することができる。
脈堅は『診家枢要』にはないため、これ以上の詳述は控えておくが、その上でさらに「以濇」を解釈すべきであろう。
濇脈が示す情報
さて、次は脈濇の解釈といこう。『診家枢要』では「氣多血少」と記される脈である。
この氣血の多少も、やはり“相対的にみた多少”として解するべきである。そして「脹」における濇を解するには、この「氣多血少」の氣血を“陰陽”に変換し直して読む必要がある。
このようにみると大脈と濇脈は同じ「相対的に陽多陰少の脈」であるといえる。
『診家枢要』濇脈より
脈濇は濇脈とは滑ならざる也。
虚細にして遅く、往来難し、三五調わず、
雨の沙を沾すが如く、軽刀の竹を刮る如し。
然るに気多血少の候と為す。
■原文
澀、不滑也。虚細而遅、往来難、三五不調、如雨沾沙、如軽刀刮竹然。
為氣多血少之候。
為少血、為無汗、為血痹痛、為傷精。。
さてこのように見れば、脹を示す脈「脈大堅以濇」とは、氣分における陰陽の偏差と不和が起こっていること。この状態がベースにあることが第一条件である。
「大堅」そして「以濇」を総合的にみると…
以上の病態を基盤として、この上に濇脈が示す病態が加わるのである。
そこで脈濇の「氣多血少」を“陽多陰少・衛多営少”として解釈すると、脹の病態が自ずとみえてくる。濇脈といえば血虚や瘀血に関する脈との認識が強いが、ここでは氣分における陰陽(すなわち営衛)交流が流利ならず、といった解釈が適するであろう。
以上をまとめると、中氣胃氣がもつ陰陽を和する機能の不全を因とし、氣分における陰陽偏差を基盤としている。その結果、衛気と営気の交流不全を「脹」とする。脹という文字から浮腫といった、水を主体とする病にもみえるが、文脈からみるとどうもそうではないようである。その論拠となるのが下線部③である。
脹という病と、営気と衛気
「衛気の身に在る也、常然として脈に並び、分肉を循る。気の行りに逆順有り、陰陽相随い、乃ち天和を得る。……(衛氣之在身也、常然並脉、循分肉。行有逆順、陰陽相隨、乃得天和。五藏更始、四時有序、五穀乃化、然後厥氣在下、營衛留止、寒氣逆上、眞邪相攻、両氣相搏、乃合為脹也。)」
この岐伯の言葉は「脹者焉生、何因而有?」という問いに対する回答である。すなわち衛気と営気の流行を解することが、脹という病態を理解するための条件であるのだ。
衛気とは「水穀の悍氣」であり、その性は「剽疾滑利」(『素問』痹論)そして「脈外を行る氣」である。では脈外を行るのであれば、どこを行るのか?
おそらくは“体表”や“皮表”“皮膚上”を流れる氣として認識している人もいるだろう。
しかし、衛気の流行に関する記載もしっかりと『素問』『霊枢』に規定されている。「分肉」である。『素問』痹論では「故循皮膚之中、分肉之間、熏於肓膜、散於胸腹。」と明記されており、『霊枢』本篇(脹論)においても「並脉、循分肉」と記されている。
痹論における「皮膚の中、分肉の間を循り、肓膜を熏じ、胸腹に散ず」という流行範囲やその機能も興味深いものがあるが、本篇の「衛気の行りにも逆順がある。しかし陰陽営衛が相い随えば、乃ち天和を得、五臓更々(こもごも)始まり、四時に序有り、五穀は乃ち化するのだ」という天地の氣と人氣との和・天人合一を解する上でも大きな示唆といえる。
また続く文にも「然る後に厥氣が下に在れば、営衛は留止し、寒気は逆上す、真気と邪気は相い攻め、両氣が相い搏つことで、乃ち合して脹を為す也。(然後厥氣在下、營衛留止、寒氣逆上、眞邪相攻、両氣相搏、乃合為脹也。)」とある。
ここでは営衛不和の続きが示されている。営衛不和により、氣の流行の停滞が起こる。停滞が起これば必然的に逆流も生じるだろう。従って文中にある「厥氣」が生じる。
厥氣が在れば、営衛の流れはさらに不順となり留止を起こす。さらに先には厥氣病態の悪化が記されている。氣の逆上が起こり、それを止めるべくして正氣が働くのだが、すでに邪となり果てた逆氣と正氣がかち合う(真邪相攻、両氣相搏)ことで「脹」という病態が形成されるのである。
この脹という病の起点の一つである「営衛」の不和は、五乱篇にある「営衛相干」にも通ずるものがある。あらゆる治法の中でも鍼灸という治療はとくに衛気と営気に深く介入することが可能な治法である。それだけに鍼灸師は両篇ともに理解を深めておく必要がある。
鍼道五経会 足立繁久
五乱第三十四 ≪ 脹論第三十五 ≫ 師第三十六
原文 霊枢 脹論第三十五
■原文 霊枢 脹論第三十五
黄帝曰、脉之應於寸口、如何而脹。
岐伯曰、其脉大堅以濇者、脹也。
黄帝曰、何以知藏府之脹也。
岐伯曰、陰爲藏、陽爲府。
黄帝曰、夫氣之令人脹也、在於血脉之中耶、藏府之内乎。
岐伯曰、三(一云“二”字)者、皆存焉。然非脹之舎也。
黄帝曰、願聞脹之舎。
岐伯曰、夫脹者、皆在於藏府之外、排藏府而郭胸脇脹皮膚、故命曰脹。
黄帝曰、藏府之在胸脇腹裏之内也、若匣匱之藏禁器也、各有次舎、異名而同處、一域之中、其氣各異、願聞其故。
黄帝曰、未解其意、再問。
岐伯曰、夫胸腹、藏府之郭也。膻中者、心主之宮城也。胃者、大倉也。咽喉小腸者、傳送也。胃之五竅者、閭里門戸也。廉泉玉英者、津液之道也、故五藏六府者、各有畔界、其病各有形状。營氣循脉、衛氣逆、為脈脹。衛氣並脈循分、為膚脹。三里而寫。近者一下、遠者三下、無問虚實、工在疾寫。
黄帝曰、願聞脹形。
岐伯曰、夫心脹者、煩心短氣、臥不安。肺脹者、虚滿而喘欬。肝脹者、脇下滿而痛引小腹。脾脹者、善噦、四肢煩悗、體重、不能勝衣、臥不安。腎脹者、腹滿引背、央央然、腰髀痛。六府脹、胃脹者、腹滿、胃脘痛、鼻聞焦臭、妨於食、大便難。大腸脹者、腸鳴而痛濯濯、冬日重感於寒、則飧泄不化。小腸脹者、少腹瞋脹引腰而痛。膀胱脹者、少腹滿而氣癃。三焦脹者、氣滿於皮膚中、輕輕然而不堅。膽脹者、脇下痛脹、口中苦、善太息。凡此諸脹者、其道在一、明知逆順、鍼數不失。
寫虚補實、神去其室、致邪失正、眞不可定、粗之所敗、謂之夭命。
補虚寫實、神歸其室、久塞其空、謂之良工。
黄帝曰、脹者焉生、何因而有。
岐伯曰、衛氣之在身也、常然並脉、循分肉。行有逆順、陰陽相隨、乃得天和。五藏更始、四時有序、五穀乃化、然後厥氣在下、營衛留止、寒氣逆上、眞邪相攻、両氣相搏、乃合為脹也。
黄帝曰、善。何以解惑。
岐伯曰、合之於眞、三合而得。
帝曰、善。
黄帝問於岐伯曰、脹論言無問虚實、工在疾寫、近者一下、遠者三下、今有其三而不下者、其過焉在。
岐伯対曰、此言陥於肉肓而中氣穴者也、不中氣穴、則氣内閉。鍼不陥肓、則氣不行。上越中肉、則衛氣相乱、陰陽相逐。其於脹也、當寫不寫、氣故不下。三而不下、必更其道、氣下乃止、不下復始、可以萬全、烏有殆者乎。其於脹也、必審其𦙳、當寫則寫、當補則補、如鼓應桴、惡有不下者乎。


.jpg?fit=120%2C80)
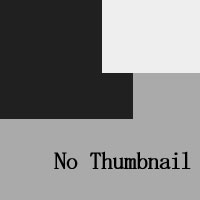



.jpg?fit=120%2C80)

.jpg?fit=120%2C80)
















 TOP
TOP