鍼道五経会の足立です。
昨日は講座『医書五経を読もう』の第1回をスタートしました。
“やさしい素問の脈診”をテーマに、脈要精微論第十七から勉強しました。
脈要精微論は「診法は常に平旦をもってす」という内容から始まります。
平旦とは明け方のことです。
ここでは「診察を行うには明け方が良い」と書かれています。しかし、実際の臨床で明け方に診察するのは不可能です。
ではこの脈要精微論の話は実際には使えない話なのか?と思われる人もいるかもしれませんが、そうではありません。
“平旦の条件”や“平旦前後の人体の動き”を理解すると、(明け方には行われない)実際の治療にも有益な情報が得られます。
また『素問』だけでなく『霊枢』を始め他の文献を開いてみると、平旦を“陰陽の交流する時”(営衛生会篇)だけでなく、“時刻でとらえる派”(『十四経発揮』・滑伯仁)と“目覚めるとき派”(『類経』張介賓)の意見があることもわかります。
『十四経発揮』滑伯仁では「…その氣常に平旦を紀とするなり。營気、常に平旦の寅時を紀とするなり。…」
『類経』張介賓「…故に診法は當に平旦、初寤の時に於いてすべし。」
この違いも考察すべき点です。
さらに『十四経発揮』と『神農本草経』、両書に記載されている平旦の内容をみることで、湯液医学と鍼灸医学のそれぞれの特性が見えてきます。
五臓未だ虚さず、六腑未だ竭きず、血脉未だ乱れず、精神未だ散ぜば、食薬必ず活く。
若し病已に成れば、半愈を得るべし。病勢已に過ぎれば命将に全うし難し。」とある。
『神農本草経』では臓腑が安定していて「食薬必ず活きる」ときを平旦の要素としているのがわかります。湯液は先ず胃の腑に方剤を投与し、胃から各臓各腑、身体各部に薬力を行き渡らせる工程が必須です。そのため臓腑の安定は方剤の効果にも影響する要因となるのでしょう。
(脈要精微論における「陰気いまだ動ぜず陽気いまだ散ぜず」に対して、神農本草経では「五臓いまだ虚さず六腑いまだ竭きず」)
これに対して、鍼灸医学の要素は時間です。『十四経発揮』では寅の刻と指定しています。十二経と十二の刻は対応していますし(後代の『子午流注』にあたる)、霊枢の各篇に時間と気の関係が記されています。
また、脈を診ること、経脈に流れや長さがあること、呼吸に定数があることからも分かることですし、そもそも生きている以上、時間とは無関係に生きていくことは不可能です。
人体にどのような時間を過ごさせるか?ということも鍼灸治療の一つの面なのでしょう。
脈を診て鍼をうつ…手慣れた治療の工程にみえるが、実は奥深い理論が鍼灸医学に包含されている。
そして打上げは通い慣れた森ノ宮の酔楽さんへ。
宴のテーマは和歌を詠むでした。歌の内容は・・・冷や汗ものでしたが、もっと勉強します…
以下は今回の勉強の範囲。
第2回の医書五経を読む “やさしい素問の脈診”は7月9日です
鍼道五経会は一緒に伝統医学を学ぶ新しい仲間を募集しています!
申し込みはコチラから
=========
【素問・脈要精微論第十七】
黄帝問うて曰く、診法は何如に?
岐伯対て曰く、診法は常に平旦を以てす。
陰氣未だ動ぜず、陽氣未だ散ぜず。
飲食未だ進まず。経脉未だ盛んならず、絡脉調匀し、
氣血未だ乱れず、故に乃ち有過の脉を診るべし。
脉の動静を切し、而して精明を視る。
五色を察し、五臓の有余不足、六腑の強弱、形の盛衰を観、これを以て参伍し、死生の分を決す。
夫れ脉とは血の府なり。
長は則ち氣治まり、短は則ち氣を病む。
数は則ち煩心し、大は則ち病進む。
上盛なれば則ち氣高く、下盛なれば則ち氣脹する。
代は則ち氣衰え、細は則ち氣少し、濇は則ち心痛す。
渾渾と革至して涌く泉の如くなるは、病進みて色弊する。
緜緜としてその去ること弦絶するが如くは死す。
=========
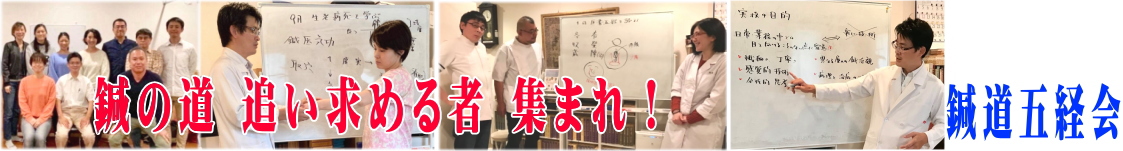

























 TOP
TOP