今回も下法の話です
今回の「注意逐邪勿拘結糞」もやはり下法のお話。
冒頭部を要約すると…「下すべき証にも諸々の所見はあるが、舌診と腹診所見がそろえば達原飲に大黄を加味して下すべし」とあります。
『傷寒論』が脉證并治…とあったように、脈診に信頼性を置いていました。
それとは対照的に、呉有性は『瘟疫論』においては、舌診にかなり信頼性を置いています。
舌診と腹診で下法の可不可を判定することを推奨しています。
この舌診と腹診へ診察のシフトは、瘟疫論における病理観をみているとなるほどと思う所です。
また興味深い点がもう一つ、「膜原から離れようとして、まだ膜原から離れていない…そんな邪に対して大黄でもって下す」という記述があることです。
何が興味深いって、邪が膜原から遊離する方向性を示している点ですね。
膜原は経と胃腑の間にあるとはいえ、邪が動く方向性は経ではなく、胃腑に向かっている(向かいやすい)ということを示唆しています。
【発病:膜原→陽明胃腑→陽明経】という病伝がひとつ見えてきます。
なので、動き始めた膜原の邪を下法によって処置するのだと。これを開門祛賊の法(門を開いて賊を追い出す)と譬えています。
(写真・文章ともに四庫醫學叢書『瘟疫論』上海古籍出版社 より引用させていただきました。)
第16章 注意逐邪勿拘結糞
瘟疫下すべき者、約するに三十餘証、悉く具えることを必せず。
但だ、舌黄、心腹痞満するを見(あらわ)せば、便(すなわち)達原飲加大黄にて之を下す。
設し邪が膜原に在る者は、已に行動の機有り、
離れんと欲して未だ離れざるの際、大黄を得て之を促して下す。
實に開門祛賊の法と為す。
即ち未だ愈ざれども、邪亦久しく羈すること能はず。(※羈;つなぐ・とめる)
二三日の後、餘邪胃に入りて仍お小承気湯を用い其の餘毒を徹す。大凡、客邪は早逐するを貴ぶ。
人の氣血未だ乱れざる、肌肉未だ消さざる、津液未だ耗せず、病人危殆に至らざるに乗じて、剤を投じ(邪を)掣肘に至らせず。
愈後亦た平復し易し。
萬全の策を為さんと欲する者は、邪の所在を知り、早く病根を抜去するを要と為すに過ぎざるのみ。
但、人の虚實を量り、邪の軽重を度し、病の緩急を察し、邪氣の膜原を離るの多寡を揣(はか)ることを要とす。
然る後に、薬を空投せず、投薬に太過不及の弊無くす。
是を以って、仲景(の方)、大柴胡より以下、三承氣を立て、多く與(あた)へ、少しく與え、
自ら軽重の殊なる有り、下(下法)に遅きを厭わざるの説に拘ること勿れ。應(まさ)に下すべき証、下して結糞無しを見て、以て之を下すこと早しと為す、或いは以て應に下すべからざるの證と為す。
誤りて下薬を投ず、殊に承気の本は逐邪と為すことを知らず而して設(まう)く。専ら結糞を為にて設くに非ざる也。
(承気湯の本意は邪を駆逐することにある。結糞・硬便があるから承気湯を処方するのではないという意であろう)必ずその糞結するを俟(ま)つときは、血液の熱の搏つ所と為し、変証迭に起る。
これ猶お虎を養いて患を遣るが如し。医の咎也。况や溏糞を下すことを失し、但だ蒸して極臭を作すること、敗醤の如く、或いは藕泥の如く(※藕=蓮根)、死に臨んで結せざる者多く有り。
但だ穢悪一たび去ることを得て、邪毒、此れに従いて消し。脉証此れに従いて退く。
豈に徒に糞結に孜孜(しし)として後に行わん哉。
假如、経枯(経閉)、血燥の人、或いは老人、血液衰少するは、多く燥結を生ず。
或いは病後、血氣未だ復せず、亦多く燥結す。
経に在りて所謂「更衣せざること十日、苦しむ所無し(※不更衣十日無所苦)」、
何の妨害か有らん。
是、燥結、人を損じること致さず、邪毒の命を殞すること為すことを知る也。邪に因りて熱を致し、熱は燥を致し、燥は結を致す、燥結して邪熱を致すこと非ざることを知るを要とせよ。但、病久しく下を失すれば、燥結之が為に壅閉し、瘀邪鬱熱して、益々泄を得難し、結糞一たび行せば、氣通じて邪熱乃ち泄する有り。
これ又前後の同じからずなり。之を總べるに邪を本と為し、熱を標と為す。
結糞も又、その標たる也。能く早くその邪を去れば、安んぞ燥結を患わんや。假令、滞下(痢疾)は本(もと)結糞無く、初起質實して、頻数窘急なる者、芍薬湯加大黄に宜しく、之を下す。
これ豈に亦結糞に因りて然らん耶。乃ち逐邪と為して設る也。
或いは曰く、積滞を為して設るを毋しとすることを得ん。
余、曰く非なり。
邪氣、下焦に客すれば、氣血壅滞し、鬱して積と為る。
若し積を去りて以て治と為せば、已成の積、方に去らん。未成の積も復た生ぜず。
須らく大黄を用い、その邪を逐去すべし。
これ乃ちその積を生ずるの源を断ち、榮衛流通す。その積、治せずして自ら愈ゆる。
更に虚痢も有り。又、この論に非ず。或いは問う、脉証相い同じく、その糞に結する有り、結せざる有り。何ぞ也?
曰く、原(もと)その人、病至りて大便當に即ち行かず、続いて蘊熱を得れば、益々出る得難し、蒸して結を為す也。
一はその人、平素より大便實せず、胃家熱甚しと雖も但、蒸して極臭を作して、状は粘膠の如く、死に至るまで結さず。應に下すべきの證、設し経論を引かば、初硬後必溏す、之を攻すべからずの(「初硬後必溏、不可攻」)句、誠に千古の弊と為す。
大承気湯・・・大黄(五銭)、厚朴(一銭)、枳實(一銭)、芒硝(三銭)
水薑煎服、弱人は半減す。邪微なる者は各々復た半減す。
小承気湯・・・大黄(五銭)、厚朴(一銭)、枳實(一銭)
水薑煎服調胃承気湯・・・大黄(五銭)、芒硝(二銭五分)、甘草(一銭)
水薑煎服
按ずるに、三承気湯の効用彷彿たり。
熱邪裏に傳うるに、但、上焦痞満する者は、小承気湯に宜し。
中に堅結有る者、芒硝を加えて(即ち大承気湯)、堅を耎し燥を潤す。
病久きに下を失すれば、結糞無きと雖も、然れど粘膩、結臭、悪物多し。
芒硝を得れば則ち大黄に蕩滌の能有り。
設し痞満無く、惟だ宿結を存して瘀熱有る者、調胃承気之に宜し。
三承気の功効、倶に大黄に在り、餘は皆な標を治するの品也。
薬湯に耐えざる者は、或いは嘔し、或いは畏る、當に細末と為し蜜丸にし湯にて下すべし。
中盤からは便の性状について論じられています。
結糞、すなわち陽明腑に熱邪が入るせいで潤いが飛ばされ、硬便となり詰まって結ぼれてしまうことです。
ここまでは『傷寒論』陽明病と同じ病理です。
しかし、この結糞を下すタイミングを失すれば、その強い熱実のためさらに「極臭を作する」とあります。
相当臭いようです。
その譬えに敗醤(オミナエシの漢名、相当臭いらしい)や藕泥といった表現があり、邪毒化した様子を伝えんとしていることがよく分かります。この結糞を下すことが、邪を排除することにつながり、熱病消退につながるということです。
しかし文中にあるように、結糞・硬便を生じる病理・生理は陽明熱の他にもたくさんあります。
例えば、血燥の状態、生理後、産後、老人などの具体例が挙げられています。
陰分の滋潤作用が低下するため、便が硬くなるのですね。
実熱の硬便と陰虚(虚熱)の硬便との鑑別が必要です。
但し、この章で呉有性が伝えたいことは結糞を下すことが目的ではないということです。
この章名にある通り「逐邪を行うのに結糞に拘泥してはならない」ということです。
結糞はあくまでも標であるとも文中にありますね。
後段では、三承気湯についての説明があります。大承気湯・小承気湯・調胃承気湯の三方は、言うまでもなく『傷寒論』方剤です。
第15章【下膈】≪ 第16章【注意逐邪勿拘結糞】≫ 第17章【畜血】
鍼道五経会 足立繁久



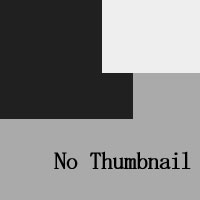




















 TOP
TOP