漢方を勉強しないのは大きな損失
漢方医の先生たちからよく聞かれる言葉
「なぜ鍼灸師さんは漢方を勉強をしないの?」
私もそう思う。『なぜ漢方を勉強しないのだろう?』『漢方をしっかり勉強している鍼灸師の先生って少ないな~』と。
東洋医学(中国医学)というからには、鍼灸と漢方ともにあってこと。
たとえ資格の問題で漢方薬を処方できなくとも、漢方医学の知識は必須なのだ。
むしろ実際に処方する経験を積めないからこそ、漢方を扱う人たちと同等かそれ以上の知識を持たないといけない…と個人的に思うところ。
実際、鍼灸院に訪れる患者さんの中に漢方を服用している人も多いだろう。
「風邪のひき始めに葛根湯」でおなじみ葛根湯を皮切りに、桂枝湯、芍薬甘草湯、小青竜湯、当帰芍薬散、桂枝茯苓丸に八味地黄丸。また、補中益気湯、清暑益気湯、六君子湯、四物湯、加味逍遙散、四逆散…など古方も後世方も含めて、いわゆる漢方薬を服用している患者さんも多いはず。
問診していて「漢方薬を飲んでいます」という場面に出くわすことも多々あるのではないかと思う。
「漢方薬を飲んでいます」と聞いて鍼灸治療をどうアレンジし対応させるのだろう?
もし漢方薬を服用していると聴いても、証立て(診断)に影響しないというのであれば、果たしてその鍼灸は東洋医学といえるのだろうか?
ちなみに昨年のハリトヒト。の推薦図書では、私の推薦図書を5冊紹介させていただいたが、5冊のうち2冊が漢方医学系の書となっている。対する鍼灸系(というか難経系)は5冊中1冊。
それほどに私は初学者には漢方を薦めているのだ。
漢方医書を読めないというだけで、読める東洋医学文献が半分以下になってしまうのだ。これは実に大きな損失だと思いませんか?
なぜ漢方を薦めるのか?
私自身の伝統医学の勉強過程を振り返ると、漢方から始まっていた。なぜか?というと、当時の私の理解力からすると『素問』『霊枢』は難しすぎた。
素問は養生や生理を説きつつも、その根底は思想書の趣きが色濃く初学者には向いていない(ように感じた)。
霊枢は鍼の技術書とはいえ、鍼に関する感性がないと理解できない(ように感じた)。
難経は陰陽五行をベースに構成されており、当時の私は陰陽五行論に対して懐疑的であったのだ(笑)
対する傷寒論は脈證併治とあるように脈(所見)から始まり、証(症状)がありそして治法というスタイルを主軸に説いてあり、素霊難の三書に比べて入りやすく感じたのだ。(それもまた浅はかな考えではあるが…)
『傷寒論輯義』(京都大学附属図書館所蔵)この多紀元簡の輯義も漢方を勉強した当時お世話になりました。
左ページ3行目、「辨(弁)太陽病・脉(脈)・證(証)・併びに治(治法)」とあり傷寒論は非常に医学的だ。
さて病理・病伝を論理的に説く医学の書として、『傷寒論』は学ぶべき書であるのは間違いない。そして鍼や灸や経穴名も『傷寒論』には登場する。つまりは鍼灸医学も加味された医学理論なのだ。
※ちなみに『傷寒雑病論』に掲載されている経穴には、風府、風池、肺兪、肝兪、関元、足陽明(衝陽)などがある。
鍼灸治療と漢方治療の違い
書から学ぶというスタイルにおいて、鍼灸系医書と漢方系医書では大きな差がでてくると私は考えている。
例えば、治療法。
治法となると、鍼灸系医書では経穴名や鍼・灸といった処方箋になるだろう。
対する漢方系医書ならば、漢方薬名、使用する生薬名とその分量が明記される。これが漢方医学としての処方箋だ。
どちらが明確かつ正確に伝わりやすいか?
私は漢方系医書だと思う。
鍼灸系医書の処方箋(経穴名・鍼or灸)では治療の詳細が伝わりにくいのだ。もちろん敢えて秘匿しているということもあるだろうが。
例えば、上に引用した『鍼灸則』(菅沼周桂)の婦人科系の章であるが、
左ページの冒頭「月経が始まってからの生理痛に悩む(経水行後而作痛)」という症状に対する処方として指示されているのは「三陰交、関元への鍼治」である。
もちろん、血虚がベースとなっている(血俱虚也)と付記されていることもあり、三陰交、関元に瀉法を選ぶ人は少ないだろうが、三陰交・関元の経穴名だけで治療できる初学者はどれだけいるだろうか?
ここでは最もシンプルな例として『鍼灸則』を挙げたのだが、実際に鍼灸治療に従事している人ほどよく分かるだろう。
仮に補法するとして、どのように補法するのか?
仮に補法できたとして、どれ位の補法が適しているのか?
鍼術は再現性に乏しいと揶揄されるが、私もそのように思う。
「師匠と同じ鍼は再現できない。」
「師匠どころか他の鍼灸師と同じ施術も再現できない。」
「自分自身が行う鍼であっても、同じ患者さんに前回と今回で同じ鍼ができるだろうか?」
(※我々が行う鍼は実験ではなく、あくまでも治療であるので、全く同じ鍼を再現する必要があるのか?というと、そうでもないのだが。)
これに対して、漢方薬ではどうだろうか?
レシピ(処方箋)さえあれば、漢方薬の構成生薬もその分量も一目瞭然である。
薬師の能力を問わず、誰が処方してもレシピを守る限り、薬物治療としては質が低下することがないのだ。
断っておくが「再現性の有無=治法の優劣」と言いたいのではない。
決して鍼灸は漢方に劣る医術ではなく、この鍼治療の再現性の低さは鍼術が持つポテンシャルだと言っても良いだろう。
しかし、こと学習・伝達・伝承という面においては、この再現性の低さが全くの不利に働く。
現代日本人は察する能力が低下している(と感じられる)ように思うし、今後それが顕著にあらわれるとも懸念している。
「一を以て十を識る(※)」という言葉を実践できる人は少ないように思う(不快に思われた方には謝ります)。
※『論語』公治長「聞一以知十」より
「月経痛(生理が始まった後 痛む)に三陰交と関元に鍼治」というフレーズから、
病理を考察し、病理に合わせた治療を組み立て、実際に診察診断した上で鍼治を再現する…と
鍼灸医書の“行間を読ませる文体”から考察を広げられる人は少ないのではないだろうか。
しかし伝統医学の書は「一を以て千も万も語る」のだ。
そう考えると、治療面での不確定要素が少ない漢方系医書の方がまだ情報を受け取りやすいといえるだろう。
しかも『傷寒論』は病理・病伝をしっかりと構築してくれている書。
病因・病理・治療方針と一貫した医学を学ぶという点で、非常に初学者向けだと考えます。
『素問』『霊枢』のような目に見えない“氣”の世界にいきなり入るのは、現代人にとってはかなり難しい学習法だとみている。
氣を感じ、認め、本当の意味で治療に活かし、折り合いをつけることができる人はそうはいないのだから。
『これ以上勉強するのは大変だな~(><)』と、つい思ってしまう人は、気を引き締め直したほうがいい。
人の体を(鍼で)傷つけて(漢方という)毒を飲ませてまで治療を行う我々は、常に学ぶ責任を感じる必要があるのです。
おまけ:漢方を学ぶメリットは他にも治療観が広がるという点もあります。
詳しくは「五行と六経・循環系と開放系」を参照ください。
もしこの記事を読んで『漢方も勉強してみようかな?』
・・・と、そんなきっかけになれば嬉しいですね。
『どうやったら漢方の勉強をできるんだろう』
と、こんな風に思った方は、一度一緒に勉強してみませんか?
大阪と東京で月に一度、鍼灸と漢方の勉強会をしています。
「鍼道五経会で学ぶ漢方医学のキホン」を参考にしてみてください。
いつでも新規メンバー募集しています!
お問合せ・お申込みはコチラのメールフォームからご連絡ください。
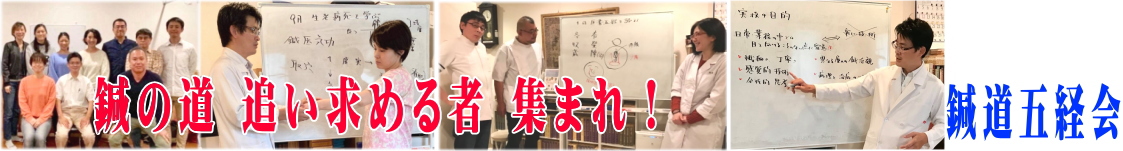



















 TOP
TOP