調胃承気湯について『古方節義』より

伝統医学の一貫性と多様性を学ぶことで道理に至る
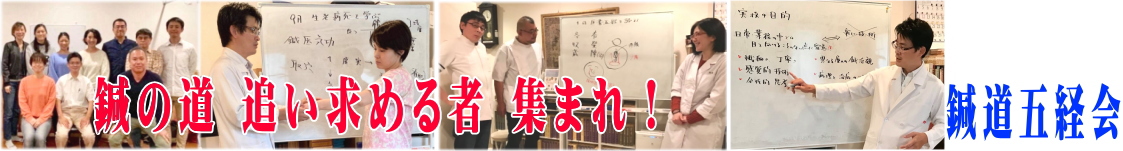

2024/06/25 | category:ゴケイメシ(五経飯)
鍼道五経会の流儀、ゴケイメシとは? 先日は講座【生老病死を学ぶ】終了後も、定例の打ち上げ・ゴケイメシを楽しみました。 鍼道五経会では、講座後の打ち上げにて、皆で料理を作って宴を楽しんでいます。文字通り「同じ釜の飯を食う仲間」です。 でも“料理を作って一緒...
読む

2024/06/11 | category:ゴケイメシ(五経飯)
6月のゴケイメシのテーマは豚肉 今回のゴケイメシのメインは豚肉をいただきました。 前回のゴケイメシで使った馬肉と豚肉が余ったので、そのまま合せ煮(一六煮)を作って保存しておいたのが今回の豚肉テーマのきっかけです。 写真:馬肉と豚肉の合わせ煮。 ...
読む

2024/05/29 | category:ゴケイメシ(五経飯)
5月の講座【生老病死を学ぶ】は… 昨日の第4日曜日は定例講座【生老病死を学ぶ】の日でした。 今回は実技多めの回でした。実技テーマは「緩急」もしくは「序破急」を意識した治療です。不明瞭なテーマなので、なかなか難度の高い実技かもしれませんが、それだけに実践的な...
読む

2024/05/13 | category:ゴケイメシ(五経飯)
5月の講座【医書五経を読む】は… 昨日の第2日曜日は定例講座【医書五経を読む】の日でした。 写真:脈診書『切脈一葦』を読むの講座風景 『切脈一葦』も下巻「邪正一源」その2まできました。その内容も実に実践的な複雑な読み取り方が必要となってきてい...
読む

2024/05/12 | category:ゴケイメシ(五経飯)
4月の講座【生老病死を学ぶ】の内容は… 先日第四日曜日は定例の講座【生老病死を学ぶ】の日。この日もお昼休みには藤の花を愛でに行きました。 写真:近くにある腰神神社には樹齢700年の藤が生えている。 写真:藤の花を愛でた後はランチで乾杯(私...
読む

2024/05/12 | category:ゴケイメシ(五経飯)
4月講座【医書五経を読む】ではお花見を堪能 4月の講座【医書五経を読む】ではお昼休みにお花見としゃれこみました。 写真:近くの願照寺さんにて枝垂れ桜をお花見 写真:桜もイイけど、この時期は楓の新緑も美しい。 脈診書を読むのコーナーで...
読む

2024/03/21 | category:講座・医書五経を学ぶ
古典を読むことで鍼灸の技術は向上するか? 【医書五経を読む】では、日本・中国に伝わる医学文献を読み解くことで、鍼灸や脈診の技術を磨きます。 鍼灸・漢方の両医学書、脈診書はもちろん、時代を問わず古典文献を丁寧に読み、東洋医学の理解を深める講座です。 ...
読む

2024/03/20 | category:講座・生老病死を学ぶ
どういう鍼灸師にあなたはなりたい? 東に病気の子どもあれば 行って小児はりをしてやり 西に疲れた母あれば 行って鍼灸産後ケアで助けるさういう鍼灸師にわたしはなりたい 2024年度の講座「生老病死を学ぶ」では産後ケア編に入ります。 産後の悩みは多岐に...
読む