先日、9月3日(第1日曜日)に定例の東京講座【臓腑経絡のキホン】を開催しました。
目次
今回は足陽明胃経の流注がテーマ
胃経は承泣・四白…から始まる・・・そんな風に覚えてしまっている人はいませんか?
鍼灸学校の授業ではそのように勉強しますよね。ところが…胃経の始まりは承泣ではないのです。胃経は頞中より始まるとあります。頞とはどの部位なのか?
このように陽明胃経の起始点を学ぶことから胃経流注の勉強を始めました。
なぜ、起始点から丁寧に学ぶ必要があるのか?経脉は人体を隅々まで流れ栄養(温め潤す)する存在です。これに絡脈を加えればさらに隙間なく体を埋める。
その様は“如環無端(環の端の無きが如し)”という言葉が言い表す通りです。流注を丁寧に学ぶことは、正確に経脈のつながりを把握するだけではありません。
なぜなら、流注の範囲を知るだけで、治療における経の活用の幅が広がるからです。
流注の範囲を知れば適応病症が増える
承泣・四白から始まる胃経流注しか知らなければ、その範囲の病症しか手に負えません。この場所であれば、例えば一部の顔面神経麻痺や副鼻腔炎などが適応疾患に当たるでしょう。
※面部の胃経の流注を図示しているところ。ちなみに足立は寝ているのではありません
しかし、起始点の“頞”という部位を視野に入れると、また胃経の適応疾患が広がります。また、ただ適応疾患が増えるだけではありません。病理の理解にまで考えが及ぶことになります。
極端な例えで恐縮ですが、鼻炎・花粉症といった疾患を五行でシンプルに分類すると“肺・金”としてのみ診てしまう(かも)でしょう。しかし、胃経流注上の病症として診ると、胃の腑から取り込んだ湿痰が胃経上に溢れている症状…という風に診ることもできます。
病理が分かれば、治療方針も具体的に立てやすくなります。このように流注を学ぶことで、病理や治療方針にまで思考は広ががるのです。
他にもニキビや頭痛…など多くの疾患に対して、このような理解は可能です。
胃経には大事な点がある・その1
鍼灸・漢方医学では“胃の氣”の存在は非常に重要です。その胃の氣と関わる胃経だけに、その流注範囲は重要な地点を通ります。
例えば缺盆や氣街といった部位もこの重要部に相当するでしょう。
缺盆を通る経脉は胃経だけではありません。足太陽膀胱経の以外の手足の陽経は缺盆にかかります。これらの意味をよく考えることも胃経を理解すること、胃・大腸・小腸・胆・三焦を理解することにつながるのだと考えています。
缺盆は毫鍼治療には使いにくい場所ですが、缺盆という場所の特性を考えるとただ禁鍼部位として片づけるのも勿体ない場所だと言えるでしょう。
胃経には大事な点がある・その2
口唇周囲、ここも経脉の流注上 重要な部位だと言えます。口唇周囲をめぐる経脈は陽明大腸経・陽明胃経はもちろんですが、厥陰肝経も口唇周りを環わりめぐります。
また、いわゆる人中(水溝穴)は任脈と督脈が交わる箇所でもあります。そして、任脈、督脈と言えば…一源三岐のもう一枝、衝脈もまた口唇周りをめぐります。
男性は髭(ひげ)が生えるのに、なぜ女性には髭(ひげ)が生えないのですか?という問答がありますが、衝脈の性質を言い表す内容です。
・・・と、このように今回の胃経流注は、人体における重要箇所にフォーカスを当ててゆっくりと読み進めていきました。
実際の講義では、これらの各内容を実践でどのように活用するか?というレベルまで掘り下げていきました。
ゆっくり丁寧な進行のため、起始部である頞から始まって気街までで中断。まだまだ胃経は掘り下げることができそうです。
次回予告・10月の内容(目標)は!?
ということで!次回10月1日の【臓腑経絡のキホン】は胃経流注の後半を行います。
胃経流注の後半と言いつつも不妊・妊娠・産後の体質に関わる内容にも触れるでしょうし、胃・土・中央を調えることで、左右・上下を調和する鍼についても一緒に考えてみたいと思います。
興味のある方はコチラのメールフォームからご連絡ください。
番外編・9月遠足は寄生虫の館へ・・・
実は…午前の部の時間を使って、目黒にある寄生虫館に見学・遠足に行ってきました。
胃の腑がテーマだけに寄生虫を…というのは後付けの理由かもしれません(笑)
寄生虫は顕微鏡などの精密機器が発達した近代医学になってから発展した分野ではありますが、伝統医学では手付かずの分野であったか?というとそうではありません。
寸白虫という呼称で、『諸病源候論』『千金要方』、もちろん『医心方』にも記載されていました。寄生虫という概念は古くからあったわけです。もちろん、肉眼で視認できる範囲にはなるでしょうが、視認できない分野は体を調えることで対処してきたのでしょう。
展示されている寄生虫標本。これだけのものが見学できて無料(タダ)!しかも撮影OKときた!ただし、飲食物は持ち込み禁止なので気をつけられたし。
エキノコックスは、国内では北海道のキタキツネを媒介とするた人体への感染が問題になっている。
近代になるにつれ寄生虫問題は減少の一途をたどるように感じるが(蟯虫・ギョウチュウはその一例)、エキノコックスなどのように、年々感染エリアを拡げている種もいる。
肉眼で確認できる寄生虫といえば、メジャー(?)かつ長大な寄生虫といえば…コレ!
サナダムシ(条虫)であろう。この標本は8メートルになろうかという長さ。巨大アナコンダやニシキヘビか!?という程のサイズである。
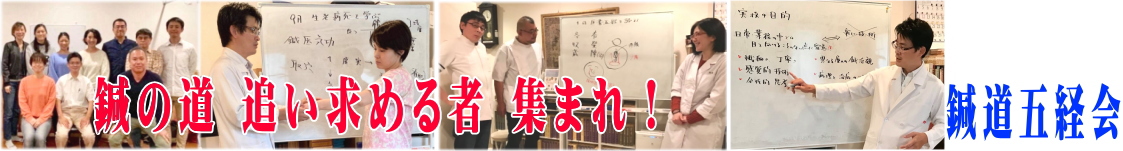
























 TOP
TOP