講座「医書五経を読む」第3期、新規メンバー募集のご案内です。本講座は『霊枢』と『切脈一葦』を読み進め、「鍼と氣」と「脈診」について学びます。
第3期の医書五経を読むは『霊枢』を読む
本講座で特に学びたいことは「素霊難における 衛気と営気を理解する」です。
『医道の日本』2020.vol.79 No.6に「診法と鍼法を一致させる―診鍼一致―」という記事を書きましたが。この記事では、診法と鍼法とが一貫しているべきであるという主張を述べました。
写真:「ツボの選び方」の向こう側という企画で診鍼一致、診鍼一貫の主旨を記事を鍼道五経会として寄稿
分かりやすく言うと、氣に対して鍼するなら氣をみる診察をしなければならない。
血を治する鍼をするなら、血をみる診察をしなければならないということです。
さらにいうと、衛気に対して鍼するなら衛気を診なければならず、営気に対して鍼をするならば営気をみる診法を行うべきなのです。そして診法だけではなく、衛気に対する鍼法・営気に対する診法を意識して行う必要はあると考えるのです。
となると、伝統医学における衛気・営気の特性を理解しなければなりません。そこで「素霊難における 衛気と営気を理解する」勉強が必要なのです。
なぜ『霊枢』を学ぶのか?
『霊枢』はまたの名を『針経』といい、鍼法・刺法そして氣について詳しく説かれています。
しかし『霊枢』を読むといっても、九鍼十二原第一から癰疽篇第八十一を全篇通して読むわけではありません。
邪道と思われるかもしれませんが “氣” に関する部分だけをつまみ食いして読み進める形になります。
しかし古典は視点を変えて読むことで、理解が変わります。氣を主体とする視点で『霊枢』を読むことは、ただ通読するよりも異なる学びが得られるだろう…と、このようにも考えています。
ではなぜ氣について『霊枢』から学び直す必要があるのか?
先ほど述べた通り、私たちは鍼治療を行う際、主に衛気に対してアプローチしているのか?それとも営気に対してアプローチしているのか?
このような問いを常に念頭に置きつつ、鍼すべきだと思うのです。そうすることで鍼の質は向上し、広い視野(例えば、この鍼法でないといけない!という固定観念からは脱け出ることができるでしょう)を持つことができます。
『霊枢』テキストはコチラのサイト記事『霊枢各篇の書き下し文と原文と…』シリーズを使用します。
脈診書も読みます
「医書五経を読む」が講座名ですので、本講座ではひろく医古文を読み進めます。
鍼法・氣の勉強を『霊枢』で行うとともに、脈診については『切脈一葦』から学びます。
『切脈一葦』はあまり知られていない脈診書ですが、江戸期の中莖暘谷氏が記した脈診書です。
脈診を知識として学ぶと“型にはまった視点”、“細かく窮屈な考え方”に囚われることが往々にしてあります。もちろん、基本を学ぶ間は大事なのですが、この考えに囚われてしまうと臨床では臨機応変に脈診を使いこなせません。
しかし『切脈一葦』の主張は一見したところ強引で型破りな説のようにみえますが、なかなか実践的かつ大胆な脈の捉え方をしています。実践的な脈診を学びたい人にとって、知っておくべき脈診書であると私は評価しています。
『切脈一葦』テキストはコチラのサイト記事『切脈一葦』シリーズを使用します。
『霊枢』に『切脈一葦』?難しそうだなぁ…
『霊枢も脈診も鍼灸師にとって必要なことはわかった。でも難しそうだなぁ・・・』と思う初級者は多いでしょう。
しかし講座内容は初級~中級向けで、もちろん参加者のレベルに合わせますので、初級者の方も大丈夫!
現在、鍼灸学校一年の参加者もいます。
質問には必ず答えるのが当会のスタンスです。先生に質問しづらい場合は先輩に質問してください。快く返答してくれることでしょう。
医書五経を読むのセミナー情報
参加条件:鍼灸師・鍼灸学生・医療関係者で東洋医学を学ぶ意欲のある方
【日 時】:毎月第2日曜日 10:30~17:00
※祝日や学会などで日程を変更する可能性があります。
※コロナ対策による自粛・非常事態宣言によってオンラインに切り替えることがあります。
【受講費】:6,000円。初参加の方は4,000円です。
※継続して参加される場合は別途 年会費が必要です。
詳しくはコチラでご確認ください
【持ち物】:スリッパ、白衣、勉強道具
【会 場】:足立鍼灸治療院。南海高野線 千代田駅から徒歩8分程度です。
【講 師】:足立繁久
講師 足立のプロフィールはコチラの【活動】を参照してください。
【申込先】:以下のメールフォームからお申込みください。
※記入されたメールアドレスにメールが届かないケースが多発しています。
複数のアドレス、もしくはTel情報を記入して申し込みください。
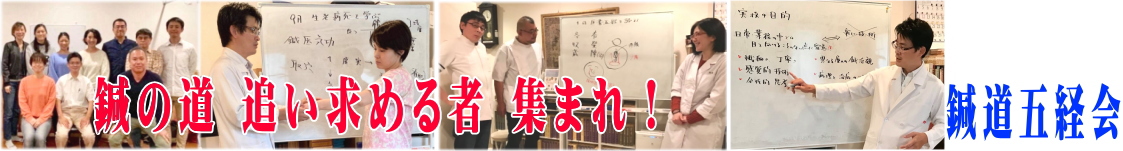

























 TOP
TOP