2月の【医書五経を読む】では、実技では鍼の補瀉と脈診鍼治の機について、そして座学は「傷寒雑病論類編の治法」を学びました。
(※脈診鍼治は造語です)
鍼の補瀉
鍼道五経会で用いる鍼の補瀉について、紹介しました。
我々が考える鍼の補瀉の基本要素は螺旋(らせん)です。螺旋には回転と方向軸すなわちベクトルが必要です。
ただ鍼を回るでもなく、上下させるでもなく、螺旋が重要なのです。
その基本となるのが天人合一の理念です。特に大気の動きを取り入れています。
そして呼吸も大事です。大気の動きと呼吸の動き、そして氣の動きは相応するものです。
この他にも、鍼の深度、虚の層と実の層に効かせる鍼、振動の要素を含む補瀉も紹介しました。
以上の要素を理解することで鍼を効かせることができるのです。
鍼を効かせるといういうより「鍼を極(き)める」というイメージです。
その補瀉の理念と技術を念頭において、次の実技を行いました。
脈診鍼治の機
当会では、脈診により診断、経穴を選択し、鍼治療を行うスタイルを提唱、実践しています。
当会に限らず、脈診により鍼治療を行う鍼灸師にとって、
鍼治により脈が変化することは当たり前の感覚だといえるでしょう。
しかし、今回の講座ではもう一段階 脈診レベルを上げるため、以下のような実技を行いました。
刺鍼後どの瞬間に脈が変化するのか?
「脈が変わる瞬間」を術者は把握できるのか?
術者によって「脈が変わる層」は異なる
…以上のことを、各自確認しました。
「脈診→病脈を判定→診断→選穴→取穴→刺鍼→効果判定」と一連の流れの中で、
刺鍼後の脈が変わる瞬間=機を把握することは、臨床上難しいですよね
ですが、この脈が変わる瞬間を把むことが大事なのです。
自分の鍼が効く瞬間を知っていないと、自分の鍼の極めどころは分からないですよね。
座学は『傷寒雑病論類編』
午後の座学は『傷寒雑病論類編』の辨愈証~辨死証~治法第四まで学びました。
人が病を得てから、どのように体が動き、どのような所見を表して変化していくのか?
ただ、病症を知識として集めて覚えるだけでは臨床では使えない知識になります。
平~病~平への一連の流れを理解することが重要です。この流れを理解すると、問診の質が変わります。
写真は、メンバーの南川先生が針道秘訣集についてプレゼンしているようす
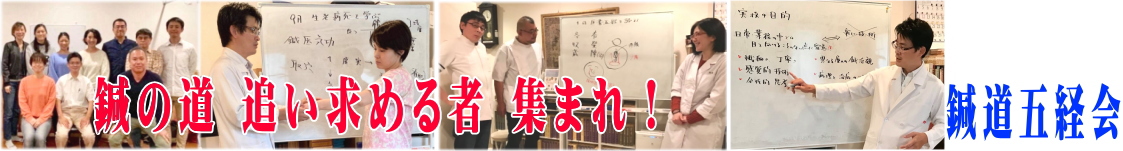

























 TOP
TOP