二十八難は奇経の役割について
【奇経を学ぶシリーズ】の難経編も4回目。
今回の二十八難は奇経の役割・機能に強調した内容である。
※『難経本義』京都大学付属図書館より引用させていただきました。
※以下に書き下し文、次いで足立のコメントと原文を紹介。
難経二十八難の書き下し文
二十八難に曰く、其の奇経八脈なる者、既に十二経に拘らざる者とある、皆 何に起き何に継ぐ也?
然り。
督脈なる者は、下極の兪に起こり、脊裏に並び、上りて風府に至り、入りて脳に属す。
任脈なる者は、中極の下に起こり、以って毛際に上り、腹裏を循り、関元に上り、咽喉に至る。
衝脈なる者は、氣衝に起こり、足陽明の経に並び、臍を夾み上行して、胸中に至りて散ずる也。
帯脈なる者は、季脇に起こり、身を廻りて一周する。
陽蹻脈なる者は、跟中に起こり、外踝を循り、上行して風池に入る。
陰蹻脈なる者は、亦、跟中に起こり、内踝を循り、上行して咽喉に至り、衝脈と交貫する。
陽維、陰維なる者は、身を維絡して、溢畜すると還流して諸経に灌漑すること能わざる者也。
故に陽維は諸陽の會に起きる也。陰維は諸陰の交に起きる也。
聖人、溝渠を圖設するも、溝渠満溢すれば、深湖に流れる。故に聖人拘り通ずること能わざる也に比す。
而して人の脈隆盛なれば、八脈に入りて、還周せず。
故に十二脈も亦これに拘ること能わず。
其れ邪氣を受け、畜すれば則ち腫熱す。之を砭射する也。
奇経の役割
本二十八難に記載されているのが、各奇経の流注・ルートとその役割である。
流注においても、我々が思い描いている奇経の流注イメージと微妙にズレを感じる点など、無いだろうか?
例えば、経穴学で任督の経穴を学ぶが、それによって自然と構築された任督のイメージと、
難経の世界における任督とでは微妙な差が生じることは往々にしてありがちなのだ。
他にも他経との関連性なども改めて確認しておくとよいだろう。
また本難で強調されているのが、溝渠の役割である。
この難経における奇経の機能もしっかりと理解しておきたいところである。
鍼道五経会 足立繁久
二十八難 原文
■原文
二十八難曰、其奇経八脈者、既不拘於十二経者、皆何起何継也。
然。
督脈者、起於下極之兪、並於脊裏、上至風府、入属於脳。
任脈者、起於中極之下、以上毛際、循腹裏、上関元、至咽喉。
衝脈者、起於氣衝、並足陽明之経、夾齊上行、至胸中而散也。
帯脈者、起季脇、廻身一周。
陽蹻脈者、起於跟中、循外踝、上行入風池。
陰蹻者、亦起於跟中、循内踝、上行至咽喉、交貫衝脈。
陽維陰維者、維絡于身、溢畜不能還流灌漑諸経者也。
故陽維起於諸陽會也。陰維起於諸陰交也。
比于聖人圖設溝渠、溝渠満溢、流于深湖。故聖人不能拘通也。
而人脈隆盛、入於八脈、而不還周。
故十二脈亦不能拘之。
其受邪氣畜則腫熱砭射之也。
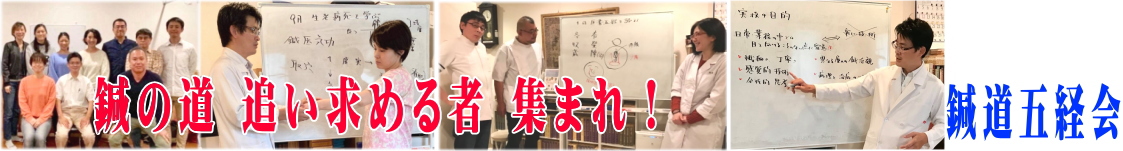

























 TOP
TOP